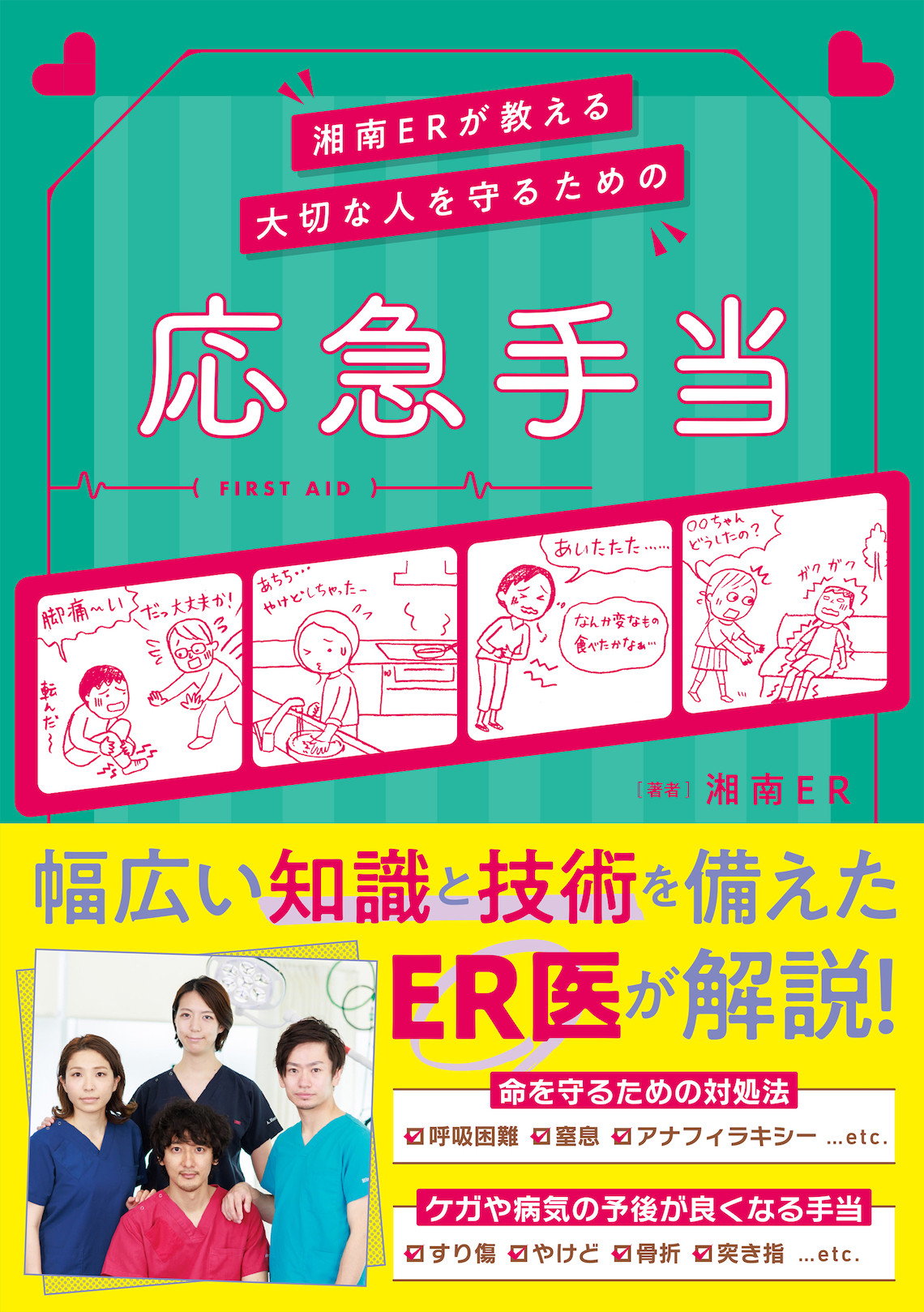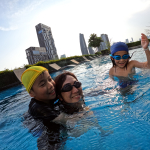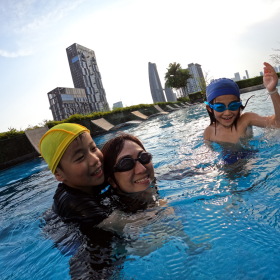いざという時にも慌てない救急箱とは?
null
湘南ERの救急総合診療科部長・関根一朗先生(インスタグラム @shonan_er)。5歳のお子さんをもつパパでもあります。
「救急箱はミニマルに」と熱弁する関根一朗先生。救急箱にあれこれ備えても、使用期限内に使い切れないケースも多く、さらにスペースもとってしまいます。それならまずは汎用性の高いものを備え、使いこなせるようになっておく方が、無駄もなくいざというときにも慌てない、と。
ただし、赤ちゃんや小さなお子さん、高齢のお年寄りなどがいる場合は、少し視点が変わるそう。
たとえば体温計の必要性が、その一例。

筆者にも7歳の子どもがおり、よく発熱するため体温計は必須。
「大人や中高生など大きなお子さんだけのご家庭なら、体感で熱が出ていると分かり、体温を計らずとも解熱剤を飲んだり病院に行ったりといった判断できます。だから体温計はなくてもいい。一方で、赤ちゃんや小さなお子さん、高齢のお年寄りがいるご家庭は、『赤ちゃんの機嫌が悪いから熱を測ってみよう』となるので体温計が必要です」(以下「」内、関根一朗先生)
このように、家族構成や持病などによって、必要なものは多少変わります。ただし次の7つは誰もが幅広く使えるので、“情報”と一緒に救急箱に備えておきましょう。
救急箱に備えるべき7つ
nullここからは、関根家にも備えているという7つの救急アイテムをご紹介します。
熱冷ましに、ケガや腹痛、頭痛などの痛み止めに「解熱鎮痛剤」
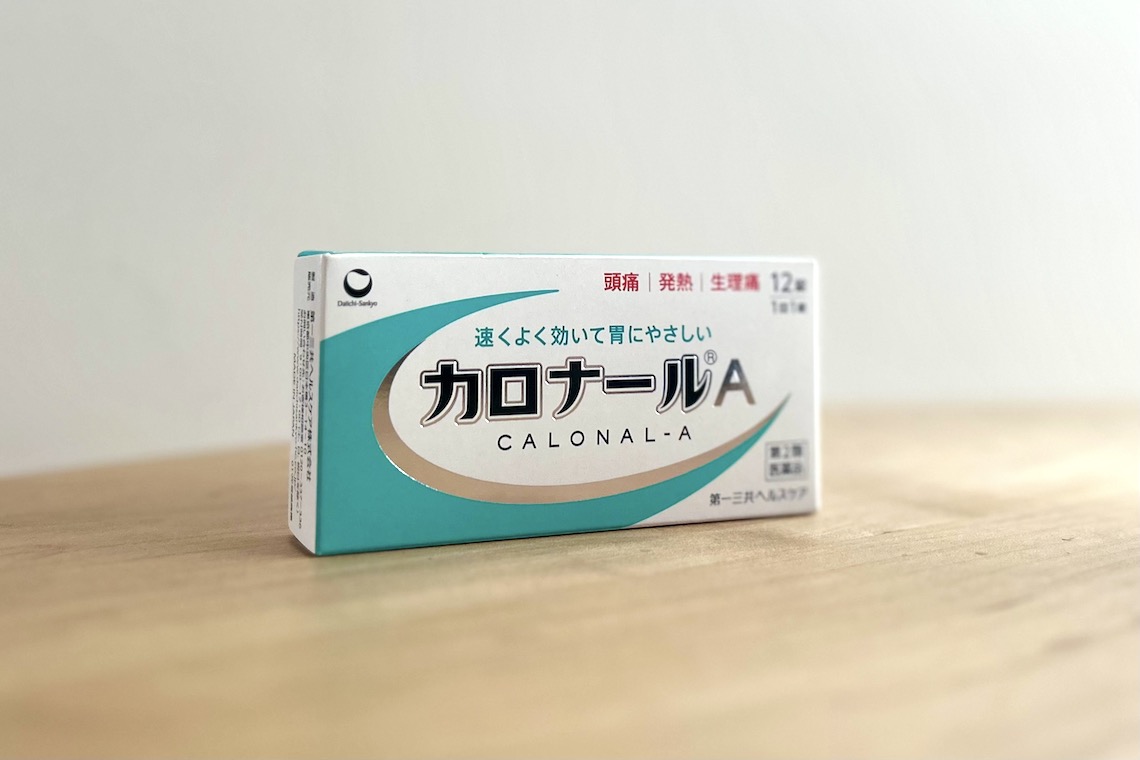
保管する場合は、買った箱のまま。使用期限や使用方法もわかるため、安心です。
解熱鎮痛剤には、大きく「アセトアミノフェン(商品名「カロナール」「タイレノール」など)」と「ロキソプロフェン(商品名「ロキソニン)」などの非ステロイド性抗炎症薬があるそうです。市販薬にも処方薬にも両方のタイプがありますが、家庭の救急箱には、胃腸への負担が比較的少ない「アセトアミノフェン」がまずおすすめなのだとか。
「お薬は、解熱鎮痛剤がいちばん汎用性が高いといえます。熱さえ下がれば、2~3日寝たら治るというケース。また、インフルエンザやコロナで熱が高くて薬を買いに行けないとき。夜でドラッグストアがしまっていているという場合にも活用できるので、解熱鎮痛剤は用意しておきましょう」
吐き気止めや咳止めなども常備している人は多いですが……?
「吐き気は発症して半日くらいでだいたい落ち着きます。また、咳は長引くと困りますが、緊急性はありません。症状が続いてつらければ、病院に行ったり薬を買いに行ったりすればいい。救急箱に備える薬は、あくまでも買いに行くまでの応急処置に絞りましょう」
ちなみに解熱鎮痛剤は、ケガの痛みを和らげたり、頭痛や腹痛にも使えるそうです。薬がたくさんありすぎる方は、絞ってみては?
塗り薬は保湿力が高い「ワセリン」が便利

赤ちゃんからお年寄りまで、使う人を選ばないのもよい。
小さなお子さんがいる、ケガしやすい、皮ふが乾燥しやすいなどといった場合に便利なのが「ワセリン」です。
「深い傷は別として、擦り傷の場合はきれいな水でよく洗い、ガーゼや絆創膏で覆います。その際に、ケガの上にワセリンを塗りましょう。これを“湿潤療法(しつじゅんりょうほう)”といい、救急医療の現場でも実践されている、傷を早くきれいに治す方法なんですよ。
ワセリンは、ヒリヒリぴりぴりする火傷やひどい日焼けにも使えますし、靴擦れの予防にかかとなどを保湿する場合にもおすすめ。赤ちゃんのおむつかぶれにもよいですよ」
脱水に「経口補水液」

用途は脱水症状のみならず。1本備えておくと安心です。
OS-1やアクアライトなどで知られる、体の成分に近い飲み物です。
「保存がきくので、非常食のような感覚で備えておきましょう。熱中症などで脱水が疑われるとき、下痢がひどいときなどに飲むといいですよ。近ごろでは、学校の保健室にも常備されていることが多いです」
また、関根先生によると、永久歯が抜けてしまった場合の応急処置にも活躍するそうです。
「口元をぶつけるなどして永久歯が抜けた場合、歯は乾燥すると元に戻せなくなります。古くから冷たい牛乳に浸すとよいとされているのですが、近年では経口補水液も有効だといわれています。浸して歯科を受診してください」
ちなみに水道水ではだめなのだとか。お気をつけあれ。
傷口を乾燥させない「ハイドロコロイド製剤」

現在の医療では、傷口は消毒しないのがスタンダードなのだとか。「しみるし、治りが遅くなるんです」。
絆創膏を備えるなら、「キズパワーパッド」などで知られる「ハイドロコロイド製剤」です。
「一般的な絆創膏より値ははりますが、傷口を早くきれいに治してくれるハイドロコロイド製剤がおすすめ。
大切なことは、汚れをきれいに水で洗ってから貼ること。汚れが残ったままだとばい菌が入って膿んでしまいます。また、市販のものはカットせず、もとのサイズのまま使いましょう。私は小指サイズを常備していますが、もう少し大きなサイズも一緒に用意しておいてもいいです」
2cm幅程度のテープがいらない「包帯」

テープ不要の「自着性包帯」が便利です。
包帯は何でもよいそうですが、便利なのは「自着性包帯(じちゃくせいほうたい)」といい、巻くだけでくっつくタイプ。
「中でも細い、2cm幅くらいのものが便利でしょう。ドラッグストアやオンラインストアなどでも売っています。傷口を適度に圧迫しやすく、巻きやすく、救急の現場でも使います」
先端がななめになった「毛抜き」

先端がななめになったものを。
ピンセット代わりになる「毛抜き」も1本備えましょう。使いやすいのは、毛抜きとしては大きめの、先端がななめのもの。
「トゲが刺さったときや、小石など傷の異物を取ったりもできます。ひどい傷は病院へ行くことをおすすめしますが、家で解決したい子どもの擦り傷などに備えておくと安心です。もちろん毛抜きにも使えますしね」
薄手の「未使用タオル」1〜2枚

筆者宅にあった未使用の銭湯タオルはちょっと派手すぎたか。
関根先生のイチオシは、銭湯で買うような薄手のフェイスタオル。
「傷口を圧迫したり、ガーゼの代わりに使ったり、ちょっと固定したいときに添えたり、嘔吐したものを拭いたり。清潔なガーゼをたくさん備えておくより、薄手の未使用のタオルも1~2枚入れておきましょう」
救急箱は「リビング」に置くのがベスト
null
「救急箱は医療の延長ではなく、あくまでも生活に即したものであるべき」と関根先生はいいます。だからこそ、小さなお子さんもお年寄りも、家族みんなが在処や使い方を知っていることも大切なのだとか。
「おすすめは、家族が集うリビングです。常温で風通しがよく、みんなが使いやすい場所に置いておきましょう。NGな置き場所は、お風呂場や洗面所の棚など、湿気の多い場所です。
入れ物は、別に“箱”である必要はなく、わが家の場合は『無印良品』の中がうっすら透ける引き出しに入れています。家用と外出用を分けず、旅行にも丸ごと持って行けるよう、“救急箱”ならぬ“救急袋”にするのもおすすめ。ソフトな素材の袋なら、中身を適度に守ってくれますよ」
外出に「+α」であるといいもの、常備薬の持ち運び方
null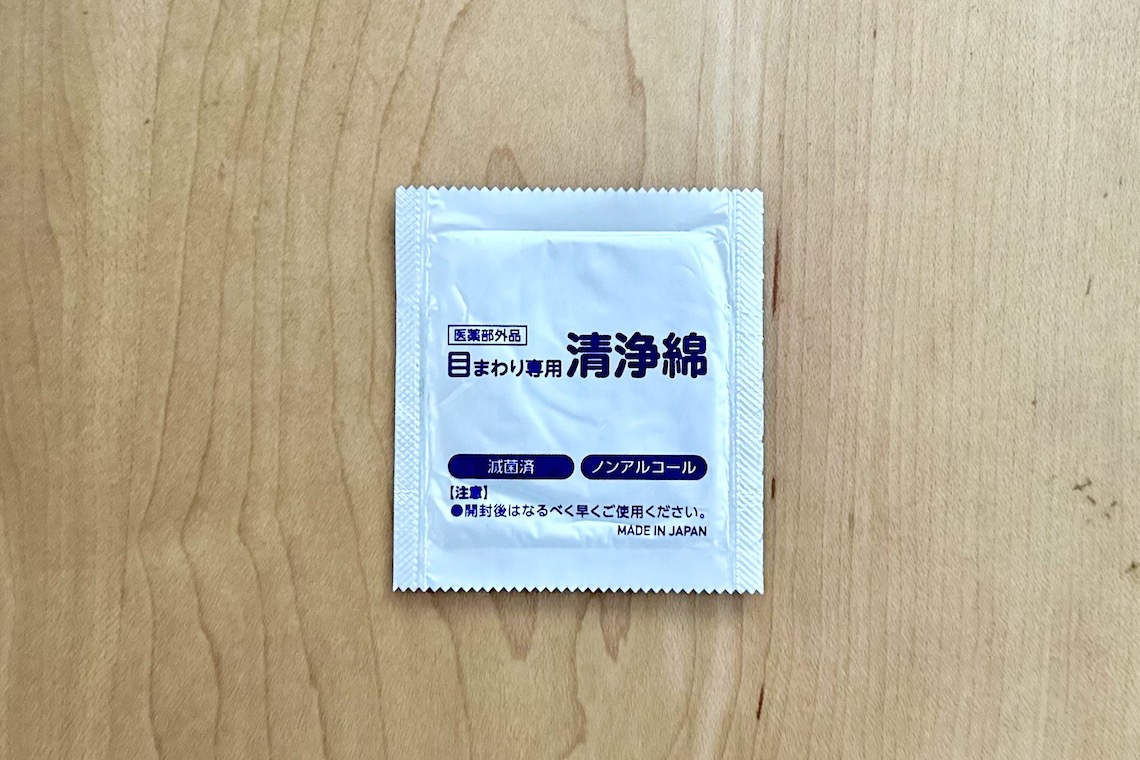
筆者は洗浄綿を持ち歩いていましたが、「わざわざ洗浄綿を用意しなくても、ウェットティッシュのほうが幅広く何でも使えます」とのこと。確かに!
外出時の万が一に備えて、+αで用意しておくと役立つものは?
「100円均一でも手に入るウェットティッシュは一つあるといいですよ。あちこち拭けますし、目に見える汚れがきれいに取り除け、ガーゼの代わりにもなります。
手指消毒や除菌のためにと、アルコール入りウェットティッシュを持ち歩く方もいらっしゃいますが、ウェットティッシュのほうが便利。というのも、アルコール入りウェットティッシュに含まれているアルコール成分が、アルコール消毒液と同じ濃度とはいえません。それに、お尻や顔、傷口などが拭けません」
また、常備薬を外出先や旅行に持っていく場合、最適解は? なるべくコンパクトに持ち運びたいですが……?
「かならず包材ごと、ピルケースや袋に入れるなどして持ち運んでください。あとで飲むからと、薬だけ裸で持ち運ぶと、品質が保たれず、適切な効果が発揮できない可能性があります。また、薬包を切り離して持ち運ぶ際も、不必要にハサミなどで1つずつに切り離さないことも大切です」
使うみんなで救急箱を見直しましょう
nullそれでなくても慌ててしまう、病気やケガのシーン。
繰り返しますが、家庭の救急箱で大切なことは、緊急時に必要な“情報”の備えと、必要最小限の汎用性の高いものを“使いこなせる”ことです。誰か一人が使いこなせても、使うみんなが在処を知らなければ困ってしまいます。
今回教えていただいた7つは、どのようなもので、どんなふうに使えばいいのか。また、家族構成などによって、何を+αするか。この機会に、使うみんなでご家庭の救急箱を見直してみませんか?

朝ランが日課の編集者・ライター、女児の母。料理・暮らし・アウトドアなどの企画を編集・執筆しています。インスタグラム→@yuknote