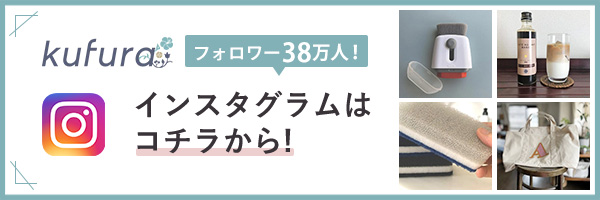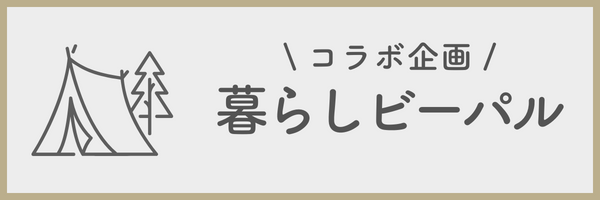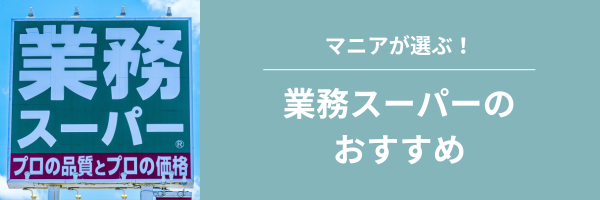“男の子のお母さん”ならではの葛藤を抱く母親の物語
null
早見さんの新刊『アルプス席の母』は、「球児の母」が主人公。令和4年7月から5年12月にかけて産経新聞夕刊(大阪本社発行)に連載された小説を、単行本化にあたって改稿しています。
息子が家からいなくなる寂しさ、強豪校を支える父母会という未知の世界……。母親のさまざまな葛藤が描かれる本作ですが、事前に読んだ書店員さんなどから大きな反響があり、なんと発売前に重版が決定。
テレビ番組『王様のブランチ』でも取り上げられ、発売から10日で4刷目の重版が決まるなど、話題を集めています。
物語は、はっとするような言葉から始まります。
山中崇(以下、山中)「ちょっと1行目を読んでみますか。(本を開いて)『本当は女の子のお母さんになりたかった』」
早見和真(以下、早見)「これ、新聞連載時は後半になってから登場した言葉だったんですよ。でも、この言葉が浮かんだとき、物語の背骨ができたような気がしました。それで改稿するときに1行目に持ってきたんです。男の子を育てるのと、女の子を育てるのとでは、母親としての人生がまるで変わりますよね」

山中崇さん
山中「そうですね。例えば息子の彼女とのシーンも、男の子のお母さんならではの葛藤があるのかなと思って面白かったです。
読んでいて感じたのは、子どもの成長とは違うペースで、母親自身も成長しているんだということ。慣れない地に移り住んで、少しずつ馴染んでいくところとか、息子の大阪弁や、『ママ』から『お母さん』、そして『おかん』と変わっていく呼び方を、葛藤しながらも少しずつ受け入れていくところとか……」
早見「母の成長は、この作品で描きたかったことでした。主人公の菜々子は、息子がまだ小さいうちに夫を亡くし、母一人子一人という環境になります。必然的に、固く絆が結ばれてしまう。でも、一方で“男の子”という生態をなかなか理解できないし、息子にぎょっとさせられることばかり。必死に子どもとの日々を過ごす過程で、溢れ出すような思いがこの人にはあるんじゃないかと。
僕はいつも、自分と世代の近い、30代から40代の男女に刺さる物語を書いているつもりなのですが、子育てに仕事にと忙しいその世代が、今、小説というものからもっとも遠くにいるような気もします。ただ今回の本では、その世代の人たち―特に男の子を育てているお母さん方を強引に振り向かせたいと思いました」
山中「読んでいて、コロナ禍で甲子園への夢を断たれてしまった球児たちの姿も連想しました。早見さんが書いた『あの夏の正解』がありましたよね。あのときの球児たち、そして、その球児たちを支えてきた親たちに向けての、早見さんの優しい眼差しを感じて……」

早見和真さん
早見「コロナ禍当時、僕は球児やその親御さんを取材していたのですが、あのとき球児たちが親に伝えていた『ありがとう』、そして親たちからの『ありがとう』―それはきっと『夢を見させてくれてありがとう』という意味だと思うんですけど、あの感謝は本物だったと思いました。
『高校球児の親』はメディアを通じて記号的に描かれることが多いのですが、ただ“見守る”だけでない母親の姿を描いてみたかったんです。高校野球というあの特殊なコミュニティを目の当たりにして、疑問を感じながらも、“息子を人質に取られているつもりで”折り合っていく母親をね」
役とはいえ…息子の苦しむ姿を見たくない母心
null
「僕が一対一で食事に行く俳優さんは、山中さんくらい」と語る早見さんと、少し照れた表情の山中さん。親しいお2人の話は尽きず、次第に自分の家族の話へと移っていきます。
早見「僕の母は10年ほど前に亡くなっているのですが、『アルプス席の母』を書くにあたっては、何度も心の中でおふくろと対話をしました。筆を止めては『あなたなら、ここで何を思いますか』と母に尋ねて、また書いて」
山中「早見さん、自分のお母さんに『ありがとう』って言ったことあります?」
早見「『チャーハンつくってくれてありがとう』くらいならあるかもしれないけど、切実な『ありがとう』は多分ないなあ」
山中「僕は21歳のときに父親が他界していますが、この年齢になって『ああ、お父さんとお酒を飲んで話せたらいいな』と、ふと思うことがあるんです。そしたら、あるとき夢に父が出てきて。夢の中で、一緒にお酒を飲んでいる。それで、自分が感謝の言葉を伝えるのかなと思ったら……めちゃくちゃ喧嘩したんですよ(笑)」
早見「面白い(笑)」
山中「亡くなったから綺麗な思いばかりが切り取られて残っているけど、実際に生きていたら、なかなか素直に『ありがとう』は伝えられないかもしれない」

早見「それが僕らの世代の親子の距離感だとも思いますね。ちょっと話が変わるけど、山中さんは大学を卒業してから、就職せずに俳優の道に進んだわけですよね。そのときご両親の反応はどうだったんですか」
山中「父はそのころ、病気がわかって入院していたんです。あるときお見舞いに行って、食堂でご飯を食べていたら『お前、金銭的に貧しくなっても、心は貧しくなるなよ』と言った。それでハッとして。当時、父に向かって『俳優になりたい』とはっきり言ったことはないけれど、学生の時から演劇をやっていたし、僕の気持ちを察していたところはあると思う。僕はその父の一言を『やってみな』と背中を押してくれたのだと捉えました」
早見「へえ~。お母さんは?」
山中「うーん、母は、反対はしないけど賛成もそんなにしない、というスタンスでした。ただ出演する舞台は必ず観に来てくれましたね。不安を抱きながらも、見守ってくれていたのかもしれないです」
早見「出演した作品に対して、お母さんから感想はあるんですか。特に『VIVANT』は周りの方からも大きな反響があったと思いますけど」
山中「僕の出演作はすべて見ていて、母から感想を言われることも多いんですけど、僕が酷い目に遭う役のときは感想を言ってこないんですよ」
早見「なるほど、面白いね。『VIVANT』で山中さんが演じたアリさんは、堺雅人さん演じる主人公に拷問されるシーンもあったから、お母さんとしては、ドラマでも『やめて』と思ったのかな」
山中「うん。だから理想の上司役を演じるほうが、母としては安心するのかもしれない(笑)」
「親をやるのは初めて」。子どもの活動に寄り添う難しさ
null
プライベートでは父親の顔も持つお2人。部活や習い事などを応援しながら、子どもと二人三脚で頑張るパパ・ママに向けて何かメッセージをいただけますかと聞くと、2人揃って「いやあ、難しいですよね……」と腕組み。
山中「僕も子育ての渦中なので偉そうなことは言えないんですけど、どうしても“こうあってほしい”という願いや期待を込めて、子どもの活動を見てしまう瞬間があると思うんです。たとえば算数の問題にてこずっているのを見ると、“できる子であってほしい”と、つい願ってしまう。でも、親から期待が少しでも溢れると、子どもにはプレッシャーになるのもわかっている。
親と子どもの歩幅は違うので、『二人三脚でやろう』と思うと、どうしたって親が先を歩いてしまいます。だから親はむしろ後ろに下がって、子どもの背中をしっかり見てあげるほうが大事なのかなと」
早見「中2の娘がいるのですが、子どものことをめぐって親は想像以上に右往左往するもんです。『部活を続けるか、やめるか』といった問題が浮上しただけで、大騒ぎですからね。いろいろ言わなきゃいけない立場だけど、この子にとっては部活をやめることの方が正解かもしれないし。『お前が思っている以上に、こっちも親をやるのは初めてだからな』と娘には言っています(笑)
そのような親としての迷いや葛藤が『アルプス席の母』にはたくさん書かれていますから、ぜひ何かのヒントにしてください。……これが僕から言えるメッセージかな」

対談の最後には、4月8日にスタートするテレビ東京開局60周年連続ドラマ『95』(早見和真さん原作、King & Prince髙橋海人さん主演)に山中さんも出演するという話題に。「俳優・山中崇を僕はとても信頼しているので、楽しみです」と早見さん。
この対談の全容は、『本の窓』ポッドキャスト(前編:5月9日、後編:5月16日公開)にて聞くことができます。ぜひそちらも合わせてお楽しみください。
取材・文/塚田智恵美
撮影/玉井美世子

早見和真(はやみ かずまさ)/写真右
1977年7月生まれ、神奈川県出身。桐蔭学園高校時代に硬式野球部に所属。大学在学中からライターとして活躍し、2008年『ひゃくはち』で小説デビュー。2014年刊行の『イノセント・デイズ』で日本推理作家協会賞、2019年の『ザ・ロイヤルファミリー』でJRA賞馬事文化賞と山本周五郎賞を受賞。
山中崇(やまなか たかし)/写真左
1978年3月生まれ、東京都出身。学生時代から演劇活動を始める。主な出演作に、大河ドラマ『鎌倉殿の13人』『おんな城主 直虎』、連続テレビ小説『ごちそうさん』『ちむどんどん』、ドラマ『深夜食堂』シリーズ、『アバランチ』、映画『アウトレイジ ビヨンド』など。5月24日に、人気猫漫画を実写化した映画『三日月とネコ』の公開を控える。

『アルプス席の母』(著・早見和真、税込1,870円、小学館)
神奈川で看護師をしながら一人息子の航太郎を育てる秋山菜々子。湘南のシニアリーグで活躍する航太郎には関東一円からスカウトが来ていたが、選び取ったのはとある大阪の新興校だった。声のかからなかった甲子園常連校を倒すことを夢見て。
息子とともに、菜々子もまた大阪に拠点を移すことを決意する。不慣れな土地での暮らし、厳しい父母会の掟、激痩せしていく息子。果たしてふたりの夢は叶うのか!? かつて誰も読んだことのない著者渾身の高校野球小説が開幕する。