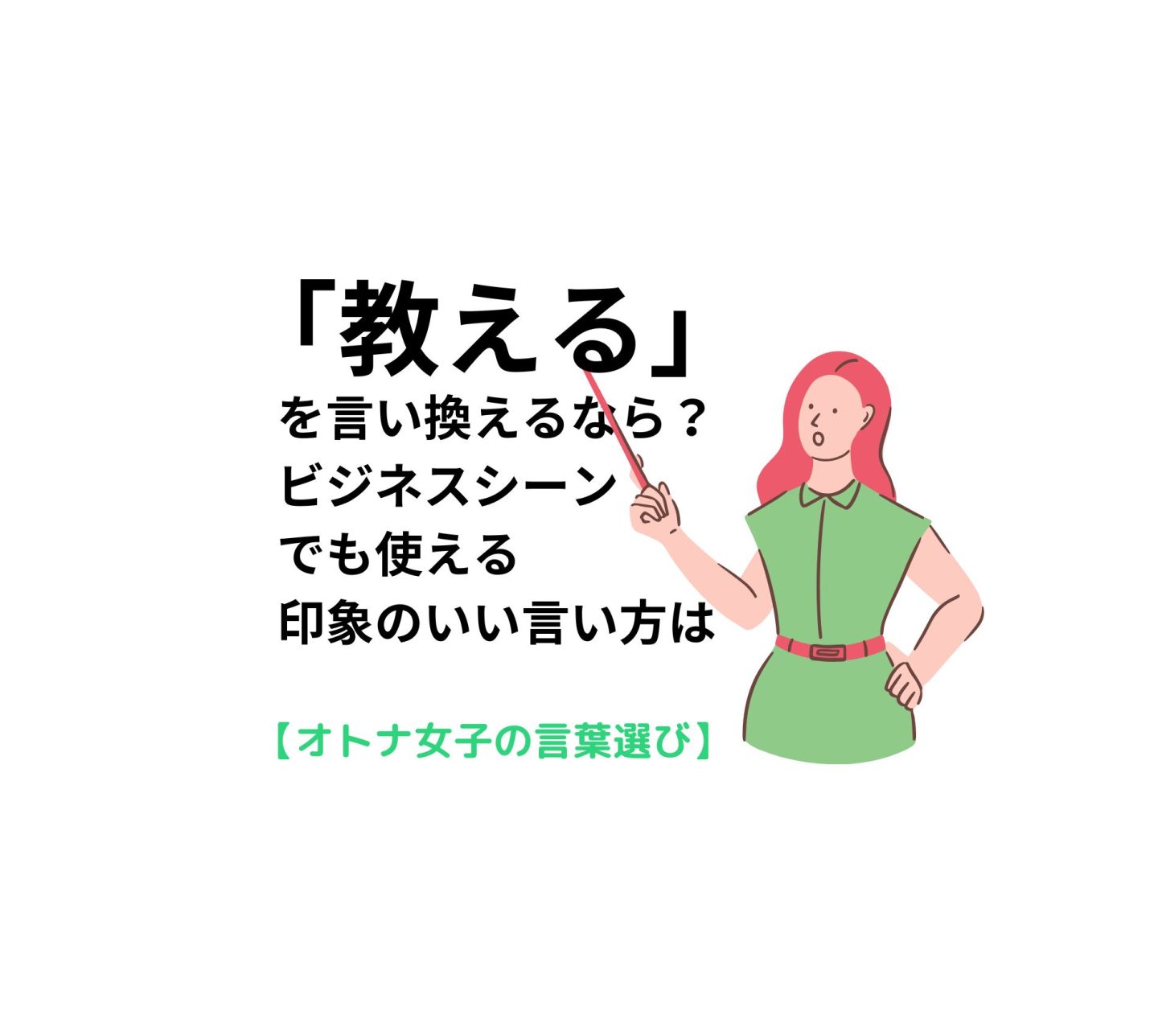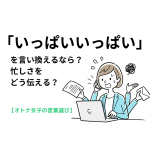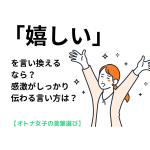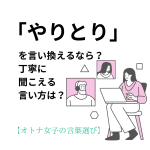「教える」の意味は?
「教える」の意味は?「教える」は、相手が知らないことを告げ示すことを意味する言葉です。指導したり、知識や技術を伝えたり、教訓を与えたりするときに使います。
一般的に、ある分野において経験が豊かな人が経験の浅い人に向けて、相手が知らない情報を与える際に使う言葉です。
「教える」を言い換えるときの注意点は?
null「教える」の言い換え表現が必要になるのは、以下のような場面です。
(1)目上の相手に「教える」場合
「教える」は、相手が知らないことを伝えるという意味があり、上下関係を想起させる言葉です。目上の相手に何かを伝える際には「教える」とは別の表現を使ったほうがいいでしょう。
【こんな使い方に注意!】
(部下から上司に)「部長にこのツールの使い方を教えてあげますね」
(2)教えてもらう立場になったときの注意点
相手に何かを教えてほしいときには、ただ単に「教えてください」というのではなく、相手の仕事を中断させてしまうことへの配慮の言葉を添えたり、相手の能力や経験に対する敬意の言葉を添えることが大切です。相手から何かを教えてもらうことは、相手の時間を使って学びや経験をおすそわけしてもらうということだと念頭に置いて依頼しましょう。
【こんな使い方に注意!】
(目上の相手に対して)「今すぐにこの作業のやり方を教えてください」
続いて、自分が教える立場、教えられる立場になったときの言い換え表現をご紹介します。
自分が「教える」ときの言い換え表現は?
自分が「教える」ときの言い換え表現は?相手に何かを伝える際、目上の相手にも使える表現をご紹介します。
【共有する】
得た情報や知見を相手に伝える際に使います。
◆例文:先方からの情報を共有いたします。
【説明する】
内容や意味を相手によくわかるように述べること。目上の相手に何かをレクチャーするときにも使うことができます。
◆例文:新しい社内ツールの使い方を説明します。
「教えてください」と依頼するときの言い換え表現は?
「教えてください」と依頼するときの言い換え表現は?相手に教えてほしいことがあるときの言い換え表現を紹介します。
【ご教示】
「教示」は、教え示すこと。具体的な情報や実践的な手続きなどを教えてもらう際に使います。
◆例文:データの格納場所についてご教示いただきますようお願い申し上げます。
【ご教授】
学問や技芸などの継続的な指導を依頼する際に使います。
◆例文:今年度の研修では、データの読み解き方について、ご教授いただきたいと思います。
【ご指導】
経験の浅い人が、経験豊かな人に教えてもらう際に使います。
◆例文:早く業務に慣れたいので、ご指導のほどよろしくお願いします。
【お知恵を拝借】
具体的な案件に関して、アドバイスが欲しいときに使います。相手の知見を敬うニュアンスを含みます。
◆例文:この件で、部長にお知恵を拝借したいと思いまして。
【伝授】
秘伝、極意などを伝え授けること。相手が現場で体得してきた知恵のようなものを授けてもらうときに使います。
◆例文:営業のコツを伝授してください。
【指南】
教えや道を示すこと。業務的なことではなく、価値観や哲学など、大きなテーマについて言うことが多い言葉です。
◆例文:社長が幹部候補の社員たちに経営の指南を始めたそうだ。
「教える」を「啓発」「啓蒙」と言い換えないほうがいい理由
「教える」を「啓発」「啓蒙」と言い換えないほうがいい理由「啓発(読み方:けいはつ)」「啓蒙(読み方:けいもう)」は、いずれも「教える」の意味を含みます。しかし、いずれも高い目線からの言葉であり、「教える」のように気軽に使うことができません。それぞれの意味を見ると、その理由がおわかりいただけると思います。
【啓発の意味】人々に知識を与え、より高い知性や理解を身に着けるように導くこと
【啓蒙の意味】無知な相手に新しい知識を与えて向上させること
知識のない相手に知識を与えるというニュアンスを含みます。「教える」と同様の使い方をしないよう、注意しましょう。
受け入れやすいように威圧感なく「教える」コツは?
受け入れやすいように威圧感なく「教える」コツは?職場や組織に属する期間が長くなると、教える機会が増えていきます。
後輩や部下に物事を伝える際には、理解しやすい言葉と、穏やかな口調、柔らかな語尾を心がけます。大切なことを教える際には、一方的に情報や知識を伝えるのではなく、すでに相手が持っている知識や経験とつなげながら伝えると、より相手に伝わりやすくなります。さらに、相手がわからないことを質問しやすい雰囲気作りにもつながっていくのではないでしょうか。
取材・文/北川和子

国語講師。「大学受験Gnoble」やカルチャースクール、企業研修などで教えるほか、「三鷹古典サロン裕泉堂」を運営。10万部突破の著著『大人の語彙力が使える順できちんと身につく本』(かんき出版)など、言葉や敬語、文章術、古典に関する発信も多い。近著に『大人に必要な読解力が正しく身につく本』(だいわ文庫)、『見るだけ・聴くだけで語彙力アップ デキる大人の話し方』(主婦の友インフォス)。東京大学卒業。