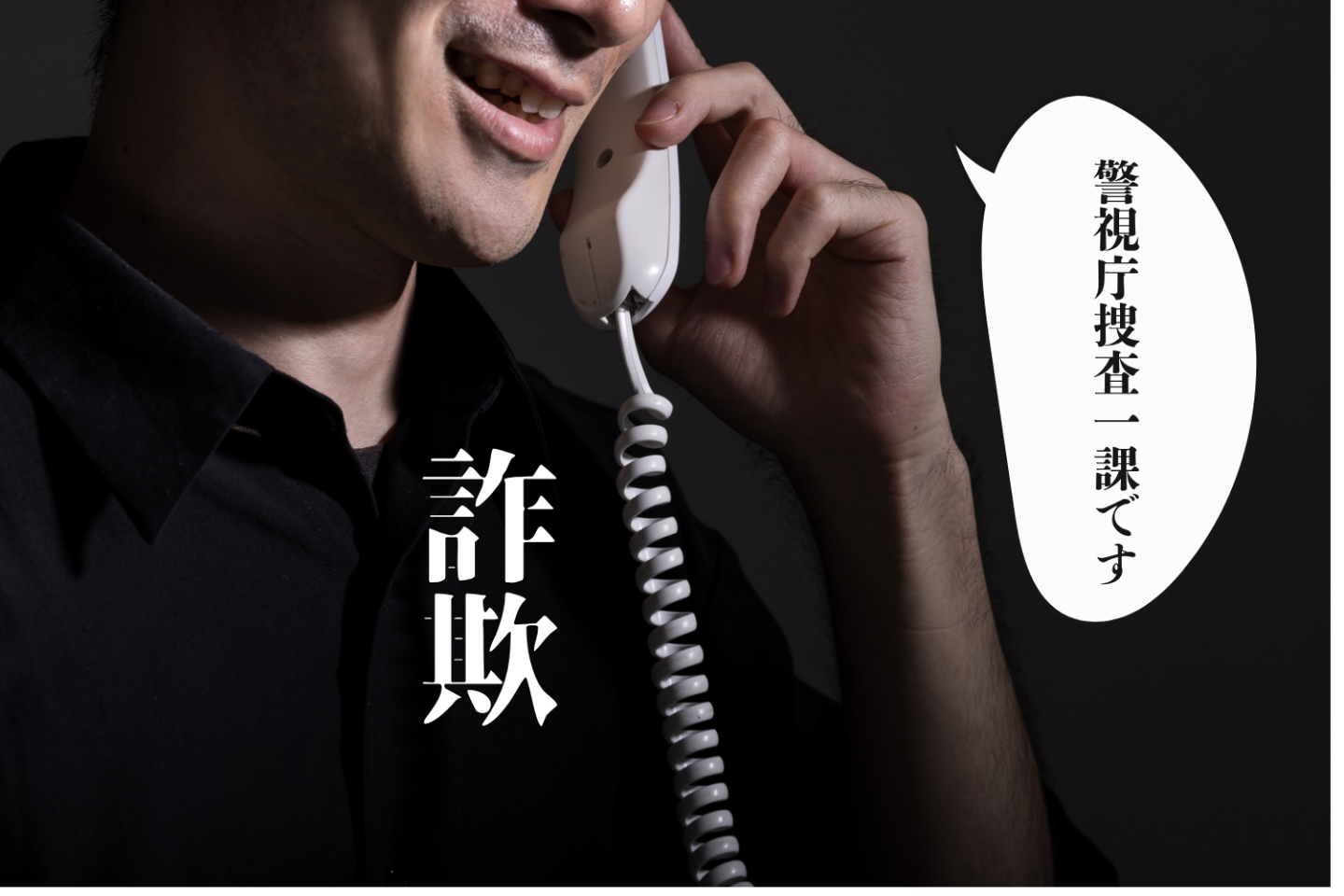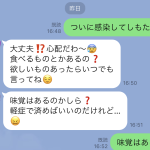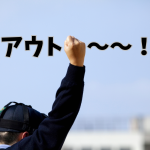4割が“詐欺に遭遇”の経験あり
null【これまでに「詐欺」に遭遇したことはありますか?】
ある・・・38.5%(136人)
ない・・・61.5%(217人)
約4割の人が詐欺に何らかの形で遭遇していることがわかりました。「思ったより多い」と感じる人もいるかもしれませんが、未遂や未然に防いだケースも含めると、詐欺は決して他人事ではありません。「自分は大丈夫」と思わず、日常のやり取りも注意が必要です。
次は、実際にみんなが遭遇した詐欺の事例です。
実に巧妙…みんなが実際に遭遇した詐欺体験
nullメールやSNS経由のフィッシング詐欺
「携帯のメールで、懸賞に当たったような内容のメールが届いたので、メールを開いてみたら、いかにも怪しいサイトだったので、いろいろ調べたら詐欺であることが分かった」(48歳男性/その他)
「SNSに企業を名乗ったものが送られてきたが、メーカーサイトとはちがうサイトへの誘導だとわかったので未然に防いだ」(50歳男性/その他)
「Xに景品に当選しましたDMがきて、LINEに誘導された」(49歳男性/コンピューター関連技術職)
「ネット銀行で詐欺対応のパスワードを強化する案内が来たが、それ自体が詐欺メールだった」(50歳女性/総務・人事・事務)
スマホやPCを使う今の時代、こうしたメールやSNS経由のフィッシング詐欺が最も多いようです。「当選」「未納」「アカウント停止」など、不安や期待をあおる文言でクリックさせようとしたり、見慣れた企業名を使うことも多く、アドレスやリンクが本物そっくりで見分けがつきにくいのが特徴です。

電話・オレオレ詐欺・なりすまし系
「NTTを名乗るところからの料金未納のため電話を止めるという内容の電話。あやしいので直接NTTに問い合わせたら同じような電話が複数確認されていて詐欺ですといわれた」(55歳男性/その他)
「オレオレ詐欺で息子を騙って金をせびるものでした。息子が高校生の時ですが試験中で確認とりにくかったこともあって危なかったです。途中で気づいて警察に通報しました」(67歳男性/総務・人事・事務)
「他県の警察官を名乗る人物から、こちらまで出頭願いますという電話がかかってきて、全く身に覚えのないよくわからない内容の話だった」(54歳女性/主婦)
「未納」「事故」「身内のトラブル」など、焦らせる内容の電話詐欺は、話すテンポや口調が自然で、信じてしまう人も多いようです。
なかには警察官や大手企業を名乗るケースもあり、信頼を利用する点が巧妙。少しでも不安を感じたら、その場で対応せず公式窓口へ確認するのが一番安全です。
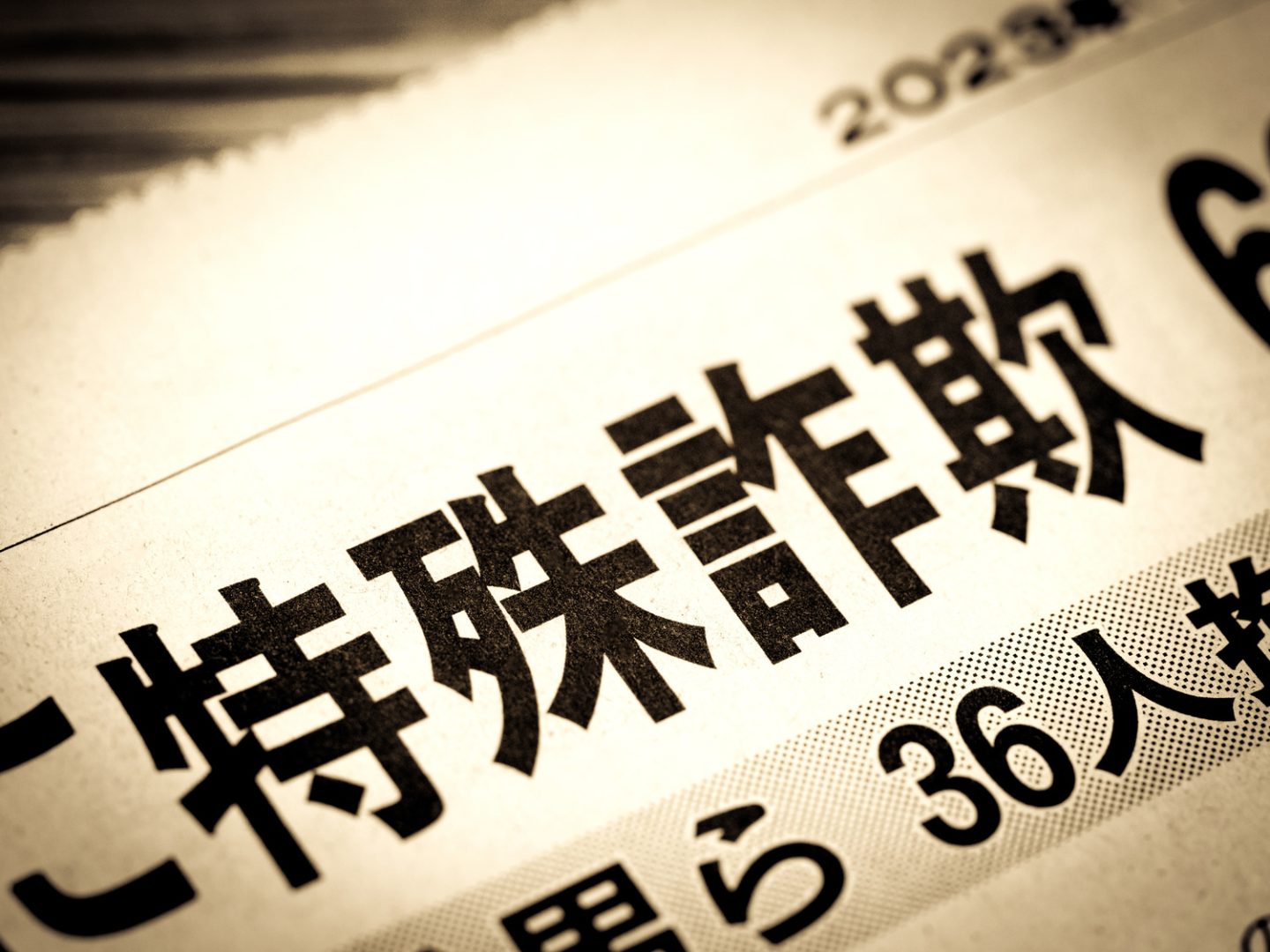
ネット通販・投資・サービス契約の詐欺
「コロナ騒ぎの時に、ア〇ゾンでマスクの出品が有ったが、注文しても品物が届かなかった」(68歳男性/その他)
「投資関係の情報を見ていたところAI投資診断なるサイトにとび、LINE友達登録したところから投資話を持ち掛けられ、話に乗ってしまった」(44歳男性/総務・人事・事務)
「無料でサプリメントでお試しを頼むと次回からバカ高いサプリメントが定期契約になっていた」(57歳男性/営業・販売)
「人気のスニーカーが格安だったので注文したらよく似た別の物が届いた」(55歳男性/その他)
「安すぎる」「すぐ儲かる」といった甘い言葉の裏には、通販詐欺や投資詐欺が潜んでいることもあります。また「お試し無料」から知らないうちに高額の定期購入契約になるなど、巧妙な手口も……。少しでも「話がうますぎる」「相場より安い」と感じたら、一旦冷静になって調べることが大切です。

ウイルス警告・不正アクセス系
「PCに『ウイルスに感染したのでここに電話を』というメッセージが表示され、電話をかけてしまった」(53歳女性/主婦)
「ウイルス感染の警告と、詐欺サイトへの誘導」(68歳女性/その他)
「知らないうちに詐欺サイトに入ってしまいクレジット情報を盗まれました」(67歳男性/その他)
突然現れる「ウイルス感染」「今すぐ対処を」という警告にはドキッとしますよね。このようなサポート詐欺では、焦って指示に従うと、遠隔操作での詐欺や金銭の要求につながることもあります。見慣れないメッセージが出たら、一度閉じて検索や確認を。慌てて電話やクリックをしないことが鉄則です。
続いて、詐欺だと気づいたポイントを教えてもらいました。コメントから見えてくるのは、ちょっとした違和感や矛盾に気づくことが被害を防ぐ決め手になっている、ということです。
なんか怪しい…詐欺だと気づいたポイントは?
null“応募してない”“身に覚えがない”違和感
「応募した覚えがなかったので検索したら詐欺の常套だった」(49歳男性/コンピューター関連技術職)
「運転免許を持っていないのに車をぶつけたとの話だったから」(66歳男性/その他)
「旅行でお世話になりました、と言ってきたが私はその土地に旅行に行ったことがなかったから」(49歳女性/主婦)
多くの人は、自分の記憶と違うと感じた瞬間に詐欺だと気づいていました。詐欺は焦らせて判断力を鈍らせようとしますが、冷静に「本当にそうだったかな?」と振り返るだけでも防げることが多いようです。少しでも違和感があったら、一度立ち止まるのが被害防止のコツですね。
“怪しい日本語・アドレス・非通知”で判明
「日本語が微妙に怪しい感じがした」(48歳男性/営業・販売)
「メアドを教えていないのにメールが届いた」(55歳女性/金融関係)
「非通知の電話番号だったからあやしい」(59歳男性/コンピューター関連技術職)
「会社名が存在しなかった」(38歳男性/総務・人事・事務)
文章の日本語がちょっと変だったり、差出人情報がおかしかったり、非通知だったり……こうした小さな違和感の積み重ねで詐欺を見抜くことができます。公式の企業や役所が非通知で電話をかけたり、無料アドレスを使ったりすることはまずありません。変だなと思ったら、迷わず削除・無視が安全ですね。
“検索”で同様の事例を確認
「ネットで調べたら同様のメールが届いて詐欺だという情報が多くのっていたので」(49歳男性/その他)
「翌日に本来のネット銀行からこのような詐欺メールがあると勧告があり、まさしく前日に受け取ったメールだった」(50歳女性/総務・人事・事務)
「ニュースで注意喚起していたから」(33歳男性/学生・フリーター)
「調べてみたら、同じ手口がたくさん出てきた」という声も多く聞かれました。インターネット上には、消費者庁や企業公式サイトなどが発信する詐欺情報の共有ページもあります。もしかして?と思ったときに検索する習慣をつけることで、被害を防げます。
最後に、みんなが実践している詐欺対策を見てみましょう。日常生活の中でどのように怪しい電話やメールを避けているのでしょうか。
詐欺を防ぐためにしていることは?
null怪しいと思ったら出ない・開かないを習慣に
「0800や+がある電話は出ない」(51歳男性/その他)
「おかしいと感じたメールや電話には出ない」(68歳男性/その他)
「知らない電話番号には出ない。変なメールが来ても削除」(54歳男性/その他)
「ネットメールの送信元のアドレスを注意深く確認し、怪しげなものは開かない」(69歳男性/その他)
最もシンプルで効果的なのは、“怪しいものには関わらない”こと。電話に出ない、メールは開かない。それだけで詐欺の大半を避けられます。つい即対応したくなるスマホ時代ですが、時には立ち止まって“スルーする勇気”を持つことが、被害を防ぐ第一歩です。

家族・知人と相談する、ひとりで判断しない
「お金が関係する話には極力夫婦で相談してから決めるようにしている」(56歳男性/総務・人事・事務)
「ひとりで判断せず、家族や信頼できる人に相談するようにしています」(35歳男性/コンピューター関連技術職)
「ひとりで対応しない。家族と常に相談したうえで対応する」(61歳男性/営業・販売)
「無視する。ひとりで判断しない、誰かに相談する」(45歳女性/主婦)
詐欺の手口は「今すぐ」や「秘密で」と急かして考える時間を奪うことが多いのだそう。だからこそ、誰かに相談するのが防御策に。身近な人と話すだけで冷静さを取り戻せることも多く、特に高齢者世帯では、情報を共有することがとても大切です。
知識・疑いの目を持つ
「『美味しい話には裏がある』『タダより怖いものはない』と自分に言い聞かせて自衛している」(58歳女性/学生・フリーター)
「簡単に稼げるものには注意している」(49歳男性/コンピューター関連以外の技術職)
「基本的に初めて接するものは疑ってかかる」(40歳女性/その他)
「警察を名乗りながら金銭を要求するのはまず詐欺と思うようにしている」(60歳男性/営業・販売)
詐欺から身を守る一番の武器は、やはり“知識”と“疑いの目”。
うまい話はない、急かされる話は怪しい、と頭に入れておくだけで行動が変わります。信じない勇気を持つことが、自分を守る大きなカギになる場合もあります。

今回のアンケートを見ると、詐欺はネット・電話・投資・買い物など、身近なシーンで誰にでも起こりうる問題であることが分かります。
・怪しいと思ったら立ち止まる
・送信元や内容を確認する
・家族や周囲と相談する
日常のちょっとした注意と確認が、自分や家族を守る力になります。今回の事例を参考に、今日からできる防止策をぜひ実践してみてくださいね。

エディター/ライター。大学在学時からライターとして活動、気付けばもうすぐフリーライター歴20年。webサイトや書籍の編集・ライティングなどを担当。料理と暮らしまわりの手仕事が趣味。根っからのインドア派だが、3児の母となりアウトドアの楽しさにも目覚めたところ。