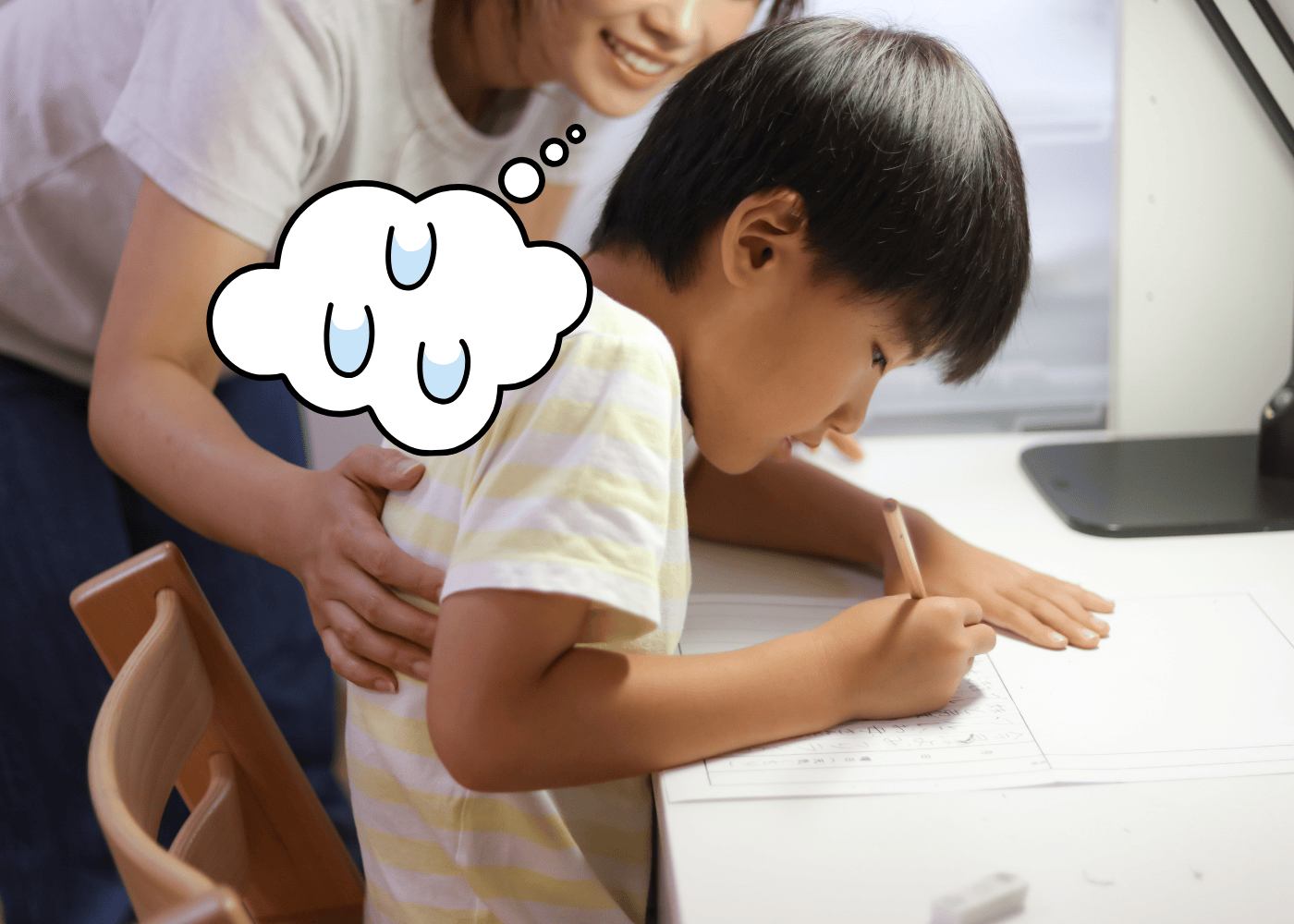第6位「習字」や「絵画・ポスター制作」…12人
null
「習字。家が汚れるかもしれないので、学校の授業内でやって欲しい」(53歳/女性/主婦)
「習字。準備などが大変だから」(42歳/男性/その他)
「絵画。絵の具で汚れるから」(51歳/女性/主婦)
「ポスター。書いて何の意味があるのか分からない」(44歳/女性/その他)
習字や絵画、防災やマナーなどの啓発ポスターの宿題は、準備や後片付けの手間に加え、作業中に汚れる心配もあることが不評の原因。もはや、前の学期で使った筆や硯、パレットなどを掃除したり買い足しが必要なものはないかを点検するいい機会と捉えて、のびのび作業するのを見守るのみ……!
第5位「なし。もっと出してほしい」…20人
null
「宿題はあるべき。9月からの授業までに忘れないよう」(57歳/男性/その他)
「ない。宿題を出してもらわないと、勉強しない」(55歳/女性/主婦)
「ない。宿題が少ないと、時間を持て余してしまうから。普段の授業のように、あって欲しい」(56歳/女性/主婦)
意外に多かったのが「宿題をもっと出してほしい」という声。この酷暑では日中の外遊びも難しいと思うと、家でできることがあるほうが1日の中での時間管理もしやすいのが親の本音。また、都心では「小学6年生になると受験する子のために宿題がなくなりました。わが家は受験をしないので、困ります!」といったお悩みも。
第4位「自由工作」…23人
null
「自由工作は半分親が手伝う宿題」(52歳/男性/営業・販売)
「工作。何を作ったら良いか分りませんし、学校へ持って行くのも、家に持ち帰るのも大変です」(44歳/女性/管理職)
「工作の課題が出るが、結局親が手伝うことになるうえ、材料費がかかったりその後の処分に困ったりしてしまうのでいらない」(24歳/女性/パート・アルバイト)
筆者が子どもの頃は廃材や不要になった日用品の容器などを使った工作が主流でしたが、最近では100均などで材料を揃えることも多く、お金も手間もかかる宿題となってしまっているよう。大作ほど、その後の処分に頭を抱える方もおり、なかには「親が作ってそれが表彰されてしまった」なんて声もありました。
第3位「絵日記など日々の記録」…26人
null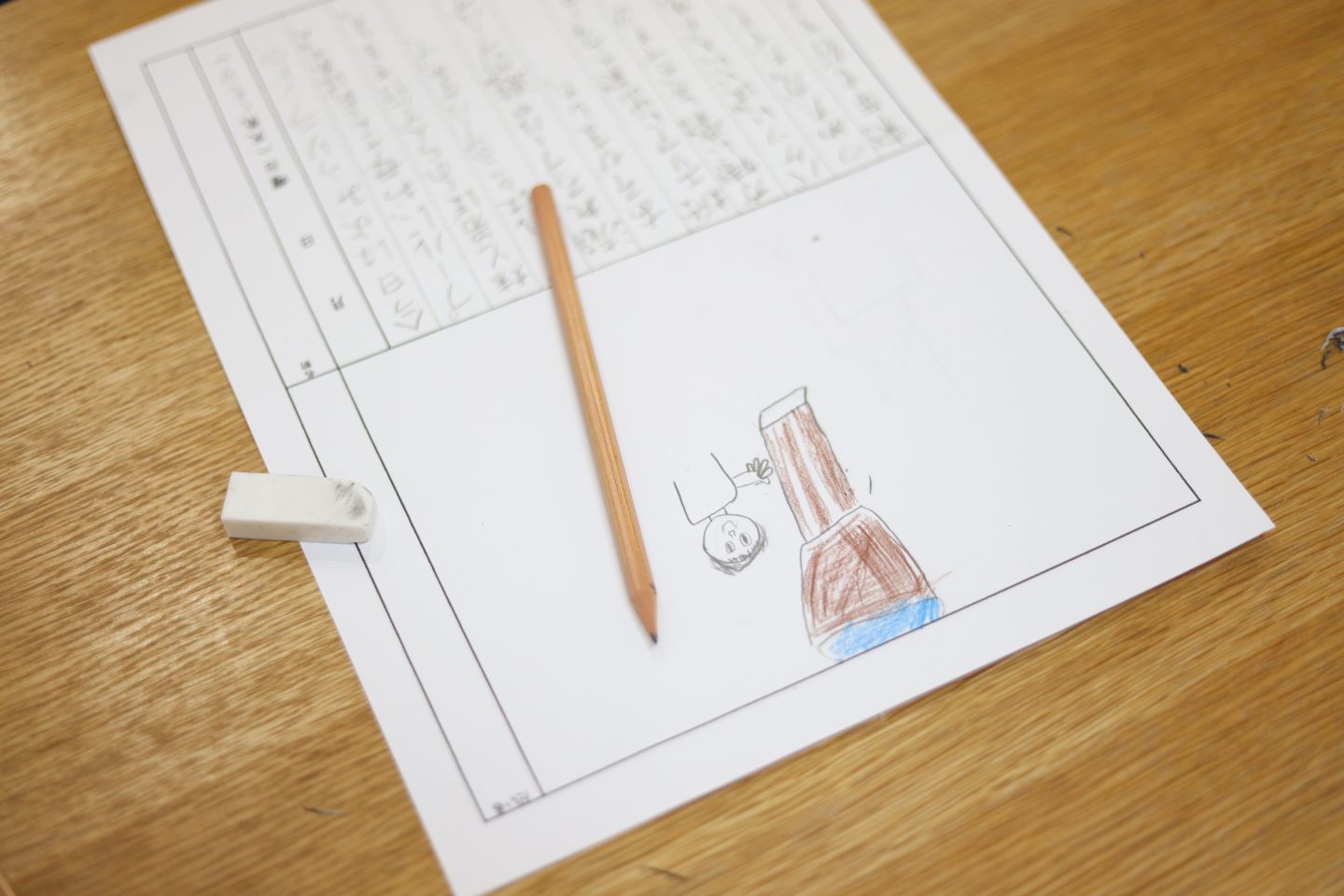
「絵日記。そんなに毎日書くことが無いから」(35歳/男性/コンピューター関連以外の技術職)
「歯磨きカレンダー。ちゃんと歯を磨いたら、その日のイラストに塗り絵をするってやつ。歯磨きはそんなことしなくても毎日すると思う……。そして歯磨きよりも塗り絵に時間がかかってる……」(33歳/女性/教職員)
「絵日記です。うちの子は毎日書かずに夏休み終盤にまとめて結構適当に書いていたので意味がないなと思いました。なので正確に言うとうちの子には“これはなくてもいい”」です」(42歳/男性/その他)
毎日コツコツと書くことが必要な絵日記やお手伝い・歯磨き・天気などの記録がTOP3にランクイン。夏休み終盤に、過去の1カ月天気を調べながら書いていた筆者の息子を思い出します……! そのほか、どこかにお出かけする経済的余裕がないからツライ、といった声も。絵日記に書くようなイベントを考えるべき?と親もプレッシャーになるようすが窺えました。
第2位「自由研究」…32人
null
「自由研究。本人がやる気ないので親が一生懸命題材実験結果を考察するハメになる」(33歳/女性/その他)
「自由研究。好きなことは勝手に自分で好きに調べると思うから、必要性を感じない」(48歳/女性/主婦)
「自由研究。自由と言いながら強制」(35歳/女性/総務・人事・事務)
僅差で第2位となったのは自由研究。創造性を育む自由工作よりも上位になったのは、知的好奇心を促して分析力まで問われるからなのか……。テーマ設定からつきっきりで面倒をみないといけないという人も多く、研究キットなどを購入するだけになるので意味がない、という手厳しい声もあがりました。
第1位「読書感想文」…33人
null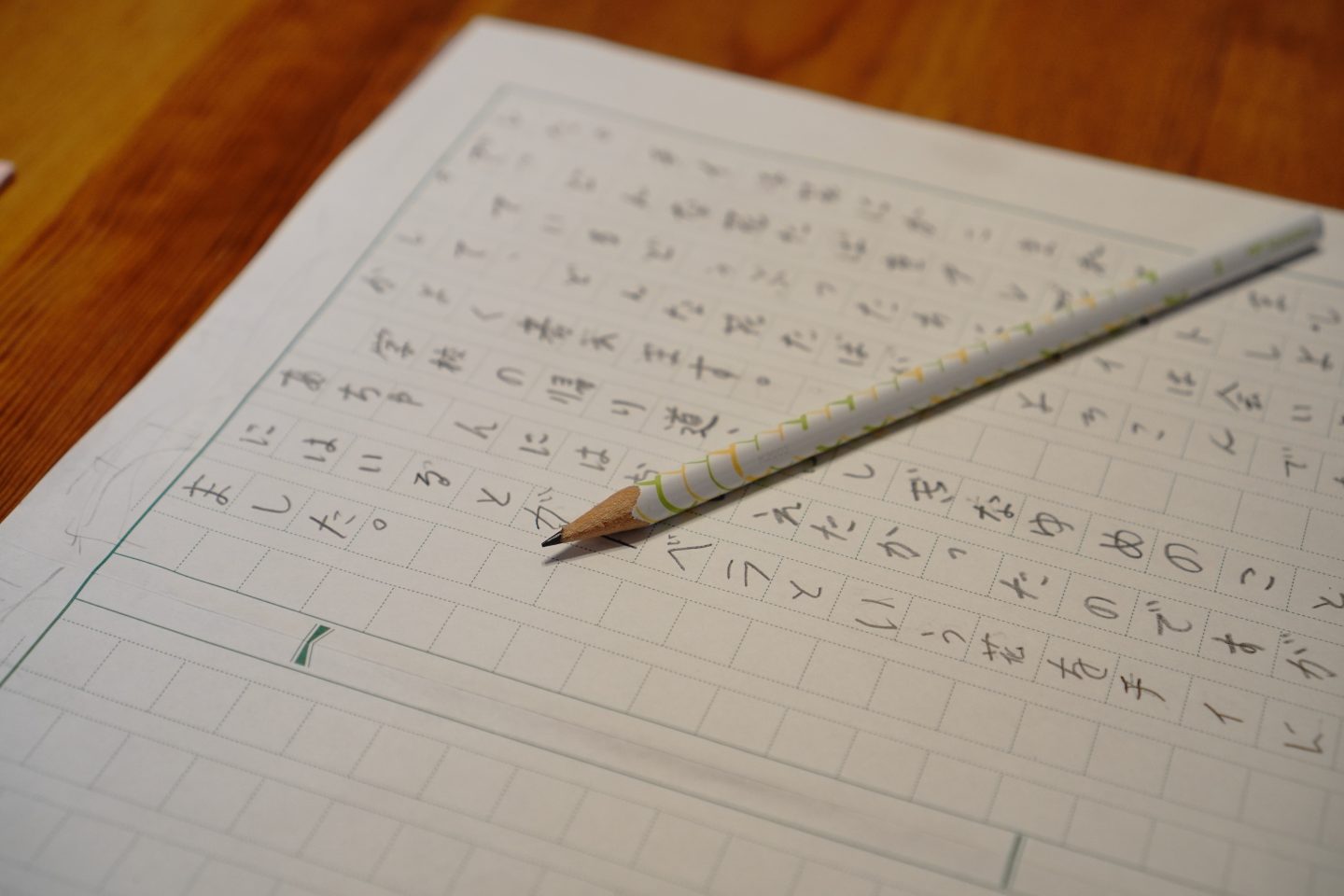
「読書感想文。理由は読書感想文は内容が薄くなりがちで、逆に読書嫌いを助長することもあると感じるから」(35歳/男性/コンピューター関連技術職)
「読書感想文。今はAIに文章作らせたりできるので不要だと思う」(47歳/男性/コンピューター関連技術職)
「本を読んだ感想なんて他人に見せるものでもないから読書感想文なんてものは要らないと思う」(49歳/男性/管理職)
「読書感想文。押し付けられた、読みたくもない本を読んで、どんな感想文が書けますか? 巻末を読んでそれをアレンジして書くのがオチで、意味がないと思います」(56歳/女性/主婦)
1票差で堂々の第1位となったのが、読書感想文。親の手が入りがちという理由のほかに、感想を書かせること自体の意義を問う声が多数! また、生成AIに頼ってしまえば宿題自体が無意味というイマドキの事情を踏まえた回答もありました。AIに頼らずとも、いまやインターネットであらすじなども把握できる時代。きちんと読んで自分の言葉で書くために親が見守る必要があると思うと、負担増になった宿題ナンバーワンかもしれません。
そのほか、こんな宿題も親にとっては困りもの!
null
「朝顔の観察日記。毎日水やり・記録を親が管理することが多く、結局“親の宿題”になってしまう。外出中や旅行中に枯れるリスクも高く、観察が途切れがち」(43歳/男性/コンピューター関連技術職)
「アイデア創作料理。子どもがひとりで写真を撮ったりできないため、親も夏休みの宿題に参加させられる始末。アイデア料理を考え、材料を用意して作り、写真まで撮影して食べた感想。忙しいママさんやお子さんがひとり以上いる家庭は大変だなぁと感じました」(39歳/女性/パート・アルバイト)
「家のお手伝い。夏休み中に形だけ手伝ってくれても子どもの習慣にはならないから」(55歳/男性/総務・人事・事務)
「答え付きの国語、算数。答えをみて一気に終わらせるから、身にはつかない」(50歳/女性/主婦)
少数派の回答も、考えさせられるものが多くあがりました。お手伝いや料理などの宿題は、各家庭の生活状況も多様ないま、それぞれのお家で親が促していくほうがスムーズに習慣化するかもしれません。とはいえ、小学校では「生活」や「家庭科」が学習科目としてあるため、先生側も保護者のサポートを期待しつつ出さざるを得ない側面がありそうです。
今回のアンケートでは、子どもだけではできない類の宿題や子どもの成長に繋がるのか不明瞭な宿題について「コレっている?」と感じる人が多い結果となりました。負担になるほどの“親のお手伝い”はほどほどに、子どもの健やかな成長を期待して自主性を尊重するというのもアリ?かもしれません。夏休み終盤に、「まだやってない、どうしよう」と親子で慌てることがありませんように……!(筆者経験談)