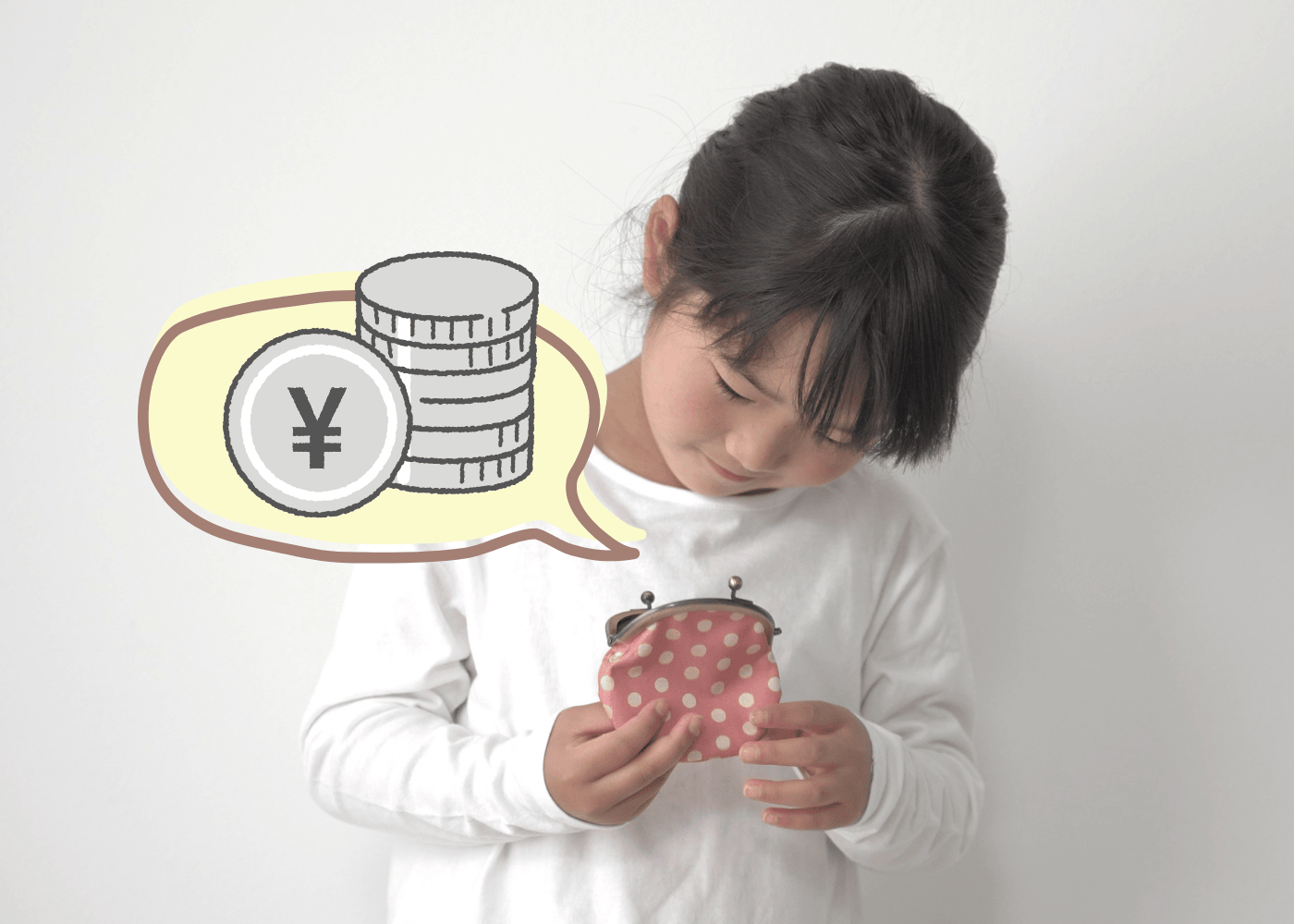小学生は定額制は少なめ…お手伝いなどでプラスすることも
null
小学生は、定期的に定額を渡しているのは5人と少なめの傾向で、必要に応じてあげていたりお手伝い制も組み合わせているという声がみられます。
「定額制だが遊びに行くとなるとお小遣いを渡したりして金額が増えている」(43歳/主婦)
「月一のお小遣いの金額は変わらず、お手伝いをしてプラスであげられるようにした」(41歳/主婦)
「お小遣い制にはしておらず、必要であれば渡す、購入するようにしている」(42歳/その他)
「高校生の子は必要に応じて渡していたけれど、物価高騰もあって月額制にした。小学生に関してはお手伝い制にしている。10回すれば100円」(49歳/主婦)
中高生になると定額をあげる家庭が増加!
null
「年度の変わり目にお小遣いについて話す機会があるが、なかなか子どもの希望にそぐわない」(53歳/主婦)
「お小遣いとして渡す金額に変化はない。ただ塾に通い始めたので、軽食費として月に1万円渡してその中でやりくりするように言っている」(52歳/主婦)
「子どものお小遣いも減らしたいが、子どもに言ったら悲しんだのでやめました」(53歳/その他)
「やはりすべての品物が高くなっているので1,000円ほど多く与えるようにした」(70歳/総務・人事・事務)
中学生・高校生になると、おこづかいを定額制にしているという家庭が一気に増加し、ほとんどが月に1度決まった額をあげているよう。中高生になると自分で買い物をする機会も多いので、月にある程度の額を使うことが多くなるのがその要因といえそうです。
ただし、この物価高騰の中では減額も厳しく、別途必要になるお金を渡していたり増額していたりと、親の負担額は増えるのもやむなし、という声がありました。
大学生以上になるとおこづかいは不要!?
null
大学生ともなると、おこづかいそのものをやめている家庭がほとんど。
「なし。大学生のときに“バイトをして稼いでください”と言ってお小遣いはあげるのを止めました。そのおかげで金銭感覚は割とシビアです」(52歳/総務・人事・事務)
「アルバイトを始めたらおこづかいはなし制度をとっています」(59歳/主婦)
「お小遣いはあげていない。そう決めていても、なかなか、あれ買ってといわれると、難しいなと思っています」(61歳/主婦)
「子どもなりに付き合いもあるので、相談されるとそれなりのお小遣いをあげている」(69歳/主婦)
大学生以上はもう成人。アルバイトをすることも踏まえておこづかいはやめる、という声が多く聞かれました。ただ、欲しいものがあって金銭的な援助を求められることもあるよう。
アルバイトといっても今話題の“103万の壁”もありますし、そもそも学業を優先して欲しいとおもうと、なかなかアルバイトだけでおこづかいを賄うのは難しいということもあるかもしれませんね。
こうしてみてみると、幼い頃は子どもの金銭管理が拙いこともあり、おこづかいについては親が主導していることが多いですが、中高生になるとおこづかいの額については親子の交渉で苦慮することもあるようです。とはいえ、物価高は子どもの生活にも影響すると考えて、子どもに苦労はさせたくないという気持ちが多く見える結果となりました。
物価高騰の歯止めが見えないなか、これからおこづかいのあり方もさらに変化していくかもしれませんね。