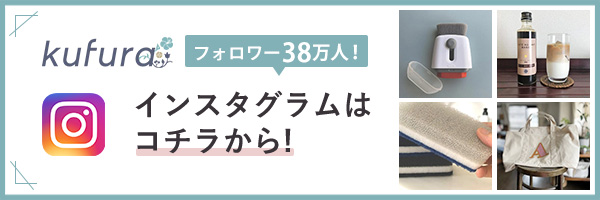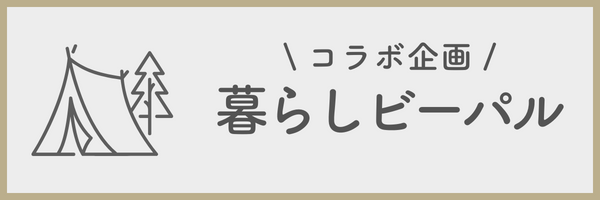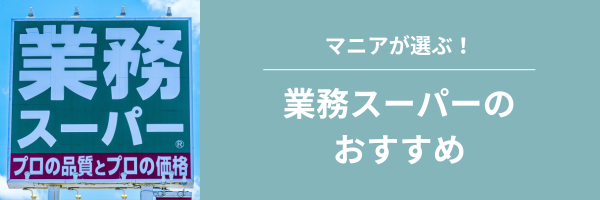「死んだら、いつでも寝られるから」
nullクリスマスのイルミネーションで華やぐ街を、家に戻る道すがら。
「北海道のばあばは、元気にしているかなあ?」
と、息子氏(9歳)が言う。
今年の春、父が亡くなった。
スキルス胃がんを宣告されてから、意識がなくなるまで、4カ月だった。
この間、私は、休みがとれるたびに実家の北海道に戻っていた。
聴覚は最後まで残ると、きっと誰かに聞いたのだろう。意識が薄くなってからも、母は父にずっと語りかけていた。
私と結婚してくれてありがとう。
私は本当に幸せでした。
これからのことは心配しないでね。
そんな会話がはじまるたび、私はそっと病室を出た。
本当に仲の良い夫婦だったのだ。
東京の私の家にいるときだって、毎晩父から電話がかかってきた。
いつも、30分以上話し込んでいる。結婚45年もたって、まだ話すことがあるんだなあと、思っていた。
息子氏は、言う。
「じいじが死んだとき、ぼく、ばあばに“大丈夫?”って聞いたことがあるの」
「うん」
「そうしたらね、ばあば、“大丈夫じゃない”って泣いてた」
「そっか……」
「ばあば、元気になっているといいなあ」
・・・・・・・・・
父と母は、教育大学の軟式テニス部で出会ったそうだ。
2人とも卒業後は学校の先生になる予定だったけれど、父は、大学4年生のとき、病を得た。卒業式にも出席できず、卒業後も就職の希望を出しながら自宅待機をすることになった。
半年後、すでに新卒採用は締め切られていた時期、父は北海道の知床半島羅臼町の小学校に赴任が決まった。当時住んでいた家からは、車で6時間かかる。地元の高校の教師になった母とは遠距離恋愛になった。
着任後、再度肺に大きな影が見つかり、父は大きな手術をすることになった。
手術は成功したものの、今度再発したら、そのときは覚悟をしてくださいと先生に言われ、リハビリを重ねて羅臼町に戻ったときは、入院から約半年がたっていたと聞く。
母は、手術を終えて羅臼町に戻った父を支えるべく、教師を辞め、知り合いが一人もいない小さな漁師町に嫁いだ。
その後、母は私を身ごもった。
私は、羅臼町で生まれ、3歳まで羅臼で育った。
当時のことを私は覚えていない。
でも、その頃を知る人たちの話によると、「5年再発しなければ……」と言われた父は、その全ての時間を、情熱を、学校の子どもたちに捧げていたようだ。当時の父の口癖は「死んだらいつでも寝られるから」だったらしい。
学校の授業中はもちろん生徒たちのために、そして放課後は軟式テニス部の選手たちのために。朝から晩まで命の全てを、クラスの子どもたち、部活の選手たちのために使った。
遠征につぐ遠征。生徒たちのために買うラケットや備品。いい先生がいると聞くと全国どこまでも飛んで練習法を聞きに行ってしまう父……。
父はお金にとんちゃくするタイプじゃなかったので、当時、母は嫁入りのときにおばあちゃんが持たせてくれたお金を切り崩して生活をしていた。そのことを話してくれたのは、私が30歳を超えてからだった。
「何のために、仕事を辞めて、嫁いできたのだろう……」
あるとき思い詰めた母は、私の手をひいて、家出をした。
もうろうとした表情で私を抱え、国道を歩いている母。その姿を不審に思った町の人に、母と私は保護されたという。
そのとき、母は、思い出したそうです。
「私は、あの人が手術をしたときに、“神様、お願いだから、命だけは助けて下さい”と、祈ったじゃないか。それを聞き届けて下さって、命を助けてもらって、さらには元気で飛び回っていることを、不満に思うなんて、おかしいじゃないか」と。
そこで、母は、父のクラスの子どもたち、部活の子どもたちと、自分自身も関わることを決めた。
毎日テニスコートに通い、そこでボール拾いをし、全ての遠征についていき、一緒に試合を応援し、一緒に喜び、一緒に悔しい思いをするようになった。
休みの日には、家にクラスの子どもたちが遊びにこれるようにし、ご飯を食べさせ、一緒に山登りをし、一緒に歌を歌うようになった。
父が死んだとき、驚いたことがある。
父が関わったクラスの教え子、テニス部の教え子、同僚の先生方の名前、講習で回った全国の先生たち、選手たちの名前を、母が全て覚えていたことだ。
父が死んでからも、教え子やその親御さんたちが、ひっきりなしに母をたずねてきてくれる。介護で痩せ細った母は、少しずつ体重を取り戻していった。
お父さんには、人の心に火をつける力がある。
父は、公開授業をすれば、教室に見学者が入りきらないほど、全国から先生がおしよせる人だった。
そして、テニスの指導者としては、小中高と、自チームや北海道選抜の16回の全国優勝に関わり、ベースボールマガジン社で7年間もの連載を執筆していた人でもある。
でも、その全てを文字通り、支えてきたのは母だった。
父は、あらゆる重要な決断は、母と相談して決めていた。彼女がいたからこそ、父はずっと走り続けることができたんだと思う。
母は、子どもの私から見ても、とても優秀な人だった。
私と弟の子育てが終わり、教職現場に復帰した後は、毎年余るほどのオファーをもらっていた。
以前、私は、母に聞いたことがある。
「ねえ、お母さんのほうが、お父さんよりずっと頭がいいし、仕事もできるのに、どうしてお父さんのサポートにばかりまわるの?」
母はこう言った。
「お父さんには、人の心に火をつける力があると思うのね。それは、本当に素晴らしいことで、誰にでもある力じゃない。だからお父さんを応援したいと思っているの」
そうか、こんなにクレバーな人が「自分が裏方にまわって支えたい」って言うくらい、父はすごい人なのか……。子ども心ながらに、そう思ったことを覚えている。
自分の人生を捧げてもいい。
そう思うほどの人に出会えた人生は、きっと幸せなものだったに違いない。
・・・・・・・・・・・
父が亡くなる日の前日、私たち夫婦は、離婚を決めた。
「お義母さんが、ずっとお義父さんに話かけている様子を見て、僕と友美さんの間にはもうきっと、ああいう時間は訪れないんだろうなと思った」
夫はそう言った。
親は、その死をもって、最後の教えを子どもに授けるという。
父と、その父を看取ろうとする母の姿が、私たち夫婦にひとつの決断を与えてくれた。
「勇気みたいなものがわいてくる感じがする」
この年末年始。
迷いに迷ったが、私は母を東京に呼ぶことにした。北海道も今は大変な時期だから、東京とさほどリスクは変わらないだろうと判断した。父のいない初めての年越し。母に一人で新年を迎えてほしくなかった。
クリスマスイブの今日、母は北海道から東京にやってくる。
それを聞いた息子氏は、いたく喜び、「ばあばにクリスマスプレゼントを用意しようよ」と言う。
そして、「ばあばは元気にしてるかなあ」と言ったのだ。
私は彼に聞いてみた。
「ねえ。じいじは、死んだあとも、キミのことを覚えていると思う?」
不思議なもので、そういう話をするとき、私たちはなぜか、空を見上げてしまう。
「うーん、わからない。でも、覚えてくれているといいなーって思う」
しばらくの間があったあと、息子氏は空から視線をおろして、自分の胸を指した。
「じいじのことを思い出すと、このへんに、勇気みたいなものがわいてくる感じがするよ」
へええ。勇気、か。
「勉強しているときとか、サッカーしているときとか、ときどき、じいじのことを思い出すことがあってね。そうしたら、なんか、頑張れるような気がするんだよね」
ああ、それはわかるな。
それは、ママも同じだ。
「じいじには、“勉強しなさい”って言われたことは一回もないから、なんか不思議だけどね」
彼は笑う。
父から受け継がれた命を。
私が受け渡した命を。
この小さな男の子の中に、見つける。
そういえば、彼を妊娠したとき。
父は、それまで一度も見たことのないような顔で、喜んでくれたっけな。
冷たい風が、夜道を吹き抜ける。
「今夜は、ほんと寒いねー」
指先に息をふきかけると、彼は私の手をとって、ジャンバーのポケットに入れてくれた。
ポケットの中で、私と彼は、手をつなぐ。
命がリレーしたあたたかさが、そこにあった。
タイトル画・中田いくみ タイトルデザイン・安達茉莉
◼︎連載・第10回は1月3日(日)に公開予定です
佐藤友美(さとゆみ)
ライター・コラムニスト。1976年北海道知床半島生まれ。テレビ制作会社のADを経てファッション誌でヘアスタイル専門ライターとして活動したのち、書籍ライターに転向。現在は、様々な媒体にエッセイやコラムを執筆する。 著書に8万部を突破した『女の運命は髪で変わる』など。理想の男性は冴羽獠。理想の母親はムーミンのママ。小学3年生の息子と暮らすシングルマザー。