果物の目標量はなぜ「200g」?
nullこんにちは、管理栄養士の宮崎 奈津季です。皆さんは普段、1日にどれくらいの果物を食べていますか? 目標は1日200gといわれていますが、具体的にどれくらいの量なのか、食べるとどんないいことがあるのかなどについてお話しします。
さて、令和6年度からスタートしている健康日本21(第三次/※)では、「果物摂取量の改善」が目標の一つとして掲げられています。この取り組みでは、1日あたり200gの果物摂取を目標値としています。しかし果物の摂取量は20〜50代の方で特に不足がちで、平均は100g程度という報告があります。
200gに設定されたのは、諸外国の状況や生活習慣病リスクに関する文献、生活習慣病予防の観点などから。しかし摂取量がなかなか増えていかないのが実情で、食生活改善の重要な課題のひとつとされています。
※「健康日本21」とは
厚生労働省が呼びかける、国民全体が人生の最後まで元気で健康で楽しく毎日が送れることを目標とした国民運動。「運動」「食生活」「禁煙」の3分野を中心に、具体的なアクションの呼びかけを、企業・団体・自治体と協力・連携をしながら推進するプロジェクト。
200gってどれくらい?
果物200gとはどのくらいの量になるのでしょうか。主な果物の目安量とそのエネルギー量をまとめてみました。

それほど多い量とは感じないかもしれませんが、“毎日”となると……? 1日分の量の例はこのようになります。
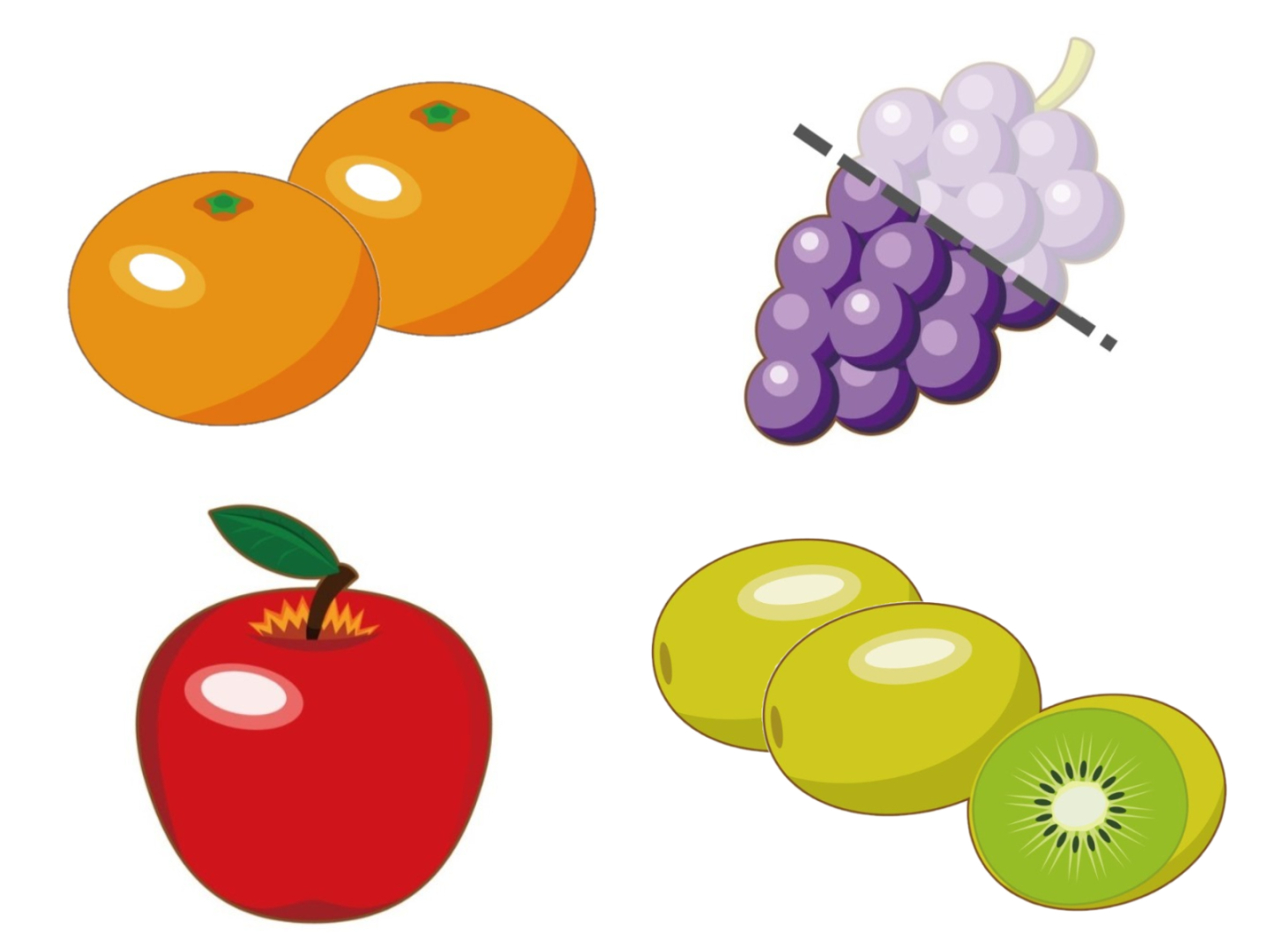
自分は普段果物をどのくらい食べているかな?と思い浮かべてみて、足りないなと感じたら意識して食生活に取り入れていきましょう。
食べるとこんないいことがある
nullビタミン、ミネラルがとれる!
果物によって含まれている栄養素の種類や量は異なりますが、ビタミンやミネラルを含んでいるものが多いです。
ビタミンの代表例としては、ビタミンC。ビタミンCは、コラーゲンの生成に必要な栄養素で、強い抗酸化作用を持っています。メラニン色素を防ぐ働きがあるため、日焼けを予防するのに役立つといわれています。

ミネラルの代表例としては、カリウム。カリウムは、細胞内の水分量を調節しており、ナトリウムとバランスをとって働く栄養素で、むくみ対策にも効果があります。血圧を下げる作用もあるため、高血圧予防にも有効とされています。また筋肉の働きを正常に保つ働きも。
不足しがちな食物繊維補給にも
果物の中には、水溶性食物繊維のペクチンを含んでいるものがあります。食物繊維は炭水化物の一つで、人の消化酵素では消化されない成分です。中でもペクチンは水に溶ける食物繊維の一つで、食べたものの粘調性を高めてゆっくりと腸を移動させることで、血糖値の上昇をゆるやかにしてくれる働きがあります。また、コレステロールの吸収を抑える働きもあるとされています。
果物を食べるときの注意点はある?
null深夜を避ければいつでもOK!「食べるタイミング」
果物を食べるタイミングは、夜22時以降は避けるとよいでしょう。これは果物に限った話ではありません。夜22時以降は時計遺伝子のひとつであるBMAL1遺伝子とそのたんぱく質が活性化されます。そのたんぱく質には、脂肪の分解を抑え蓄積する働きがあるため、「夜食べると太る」と言われるのです。

その時間帯以外であれば、とりやすいタイミングで食べればOK。朝食のときはもちろん、14~15時ごろに間食として食べるのもおすすめ。お菓子を果物に置き換えればずっとヘルシーですね。
食べすぎに注意

ついつい何個も食べちゃう「コタツにみかん」にも注意!
さまざまな栄養素を含んでいる果物ですが、もちろんどれだけ食べてもよいというわけではありません。食べ過ぎてしまうと、果糖およびエネルギーの過剰摂取につながり、中性脂肪の増大や肥満に影響する可能性があります。
糖質が気になる方は、柑橘類やキウイフルーツなど比較的糖質が少ない果物を選ぶようにしましょう。いずれにしても1日200g程度が目安量であることは忘れないで!
ジュース、加工品でもいいの?

ジュースや缶詰などの加工品は、砂糖が添加されていることが多いため、あまりおすすめはできません。また、加工や加熱により、生の状態と比べるとビタミンやミネラルなどが失われていることが多いでしょう。できれば生の果物をとるようにしてください。
皮を剥くのが面倒という人は、最近スーパーやコンビニなどで見かけるカットフルーツなどはいかがでしょうか。
健康や美容にも欠かせない果物。自分にあったとり方を見つけられると良いですね。
【参考文献】
・飯田薫子、寺本あい:「一生役立つ きちんとわかる栄養学」、西東社(2019)
・吉田企世子、松田早苗:「正しい知識で健康をつくる あたらしい栄養学」、髙橋書店(2021)
・香川明夫「はじめての食品成分表 八訂版」女子栄養大学出版部(2022)
・農林水産省「毎日くだもの200グラム!」(閲覧日:2024年4月10日)
・厚生労働省「健康日本21(第三次)」(閲覧日:2024年4月15日)
・文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(閲覧日:2024年4月15日)
・厚生労働省健康局健康課栄養指導室「【資料2】健康日本21(第三次)について~栄養・食生活関連を中心に~」(閲覧日:2024年4月15日)
・厚生科学審議会地域保健健康増進栄養部会、次期国民健康づくり運動プラン(令和6年度開始)策定専門委員会、歯科口腔保健の推進に関する専門委員会「健康日本21(第三次)推進のための説明資料」(閲覧日:2024年4月15日)
・厚生労働省 e-ヘルスネット「果物」(閲覧日:2024年4月15日)
・厚生労働省 e-ヘルスネット「睡眠と生活習慣病との深い関係」(閲覧日:2024年4月15日)
・農林水産省「『食事バランスガイド』について」(閲覧日:2024年4月15日)

管理栄養士・薬膳コーディネーター。介護食品メーカーで営業を2年間従事した後、フリーランスの管理栄養士に。料理動画撮影やレシピ開発、商品開発、ダイエットアプリの監修、栄養価計算などの経験あり。 現在は、特定保健指導、記事執筆・監修をメインに活動中。
X:https://twitter.com/NatsukiMiyazak1
※「崎」は正式には立つ崎(たつさき)です























