とにかく少しでも貯金すべし!
null
「若いときはどうしても無駄なことにお金を使ってしまうが、毎月キチンと貯金しておくこと。そうすれば老後の今、少ない年金でこんな苦しい生活をしなくてもよかったんではないかと思います」(85歳男性/その他)
「人間は、お金がないと何もできません。特に老後は介護があります。お金がないと惨めですよ。今から少しでも貯金をしてください」(74歳男性/その他)
「年金はあてにならないのでしっかり貯金を。株などで一攫千金を目指すのは絶対ダメ」(83歳男性/その他)
「給料からの自動積立。天引きだから手間いらず」(77歳男性/その他)
今回のアンケートでまず多かったのは、「若いうちからコツコツと貯金に励むべし」とのアドバイス。仕事をリタイアして収入は減るのに、医療や介護にかかる費用は増える一方で、年金だけではとても安心して暮らすことができません。
昨今の物価高の影響で、いくら節約しても手元にお金が残らない……という場合、コメントにもあるように、毎月給与口座から貯蓄用口座へ一定額を振り替える自動積立などを活用して、少しでも老後の貯えを増やすのも一考でしょう。
投資も視野に入れるべし!
null
「貯金はそのまま寝かしておくのではなく、NISAや投信などで増やしていきたい」(69歳男性/総務・人事・事務)
「iDeCoなど税制優遇のある積み立てはしておいたほうがよい。老後にお金はいくらあってもありがたいもの」(66歳男性/企画・マーケティング)
「老後の糧にするなら、若いときから株取引を少しずつ実践すべし。経験を積んでおくことは将来の生活に大変役立ちます」(80歳男性/その他)
単に貯金するだけでなく、より積極的に資産を増やせるように、投資をすすめる声もありました。たしかに、“コツコツ貯金”派からは、「投資にはリスクがあるから、投資よりも貯金が堅実」との意見も出ていますが、たとえ投資で損をしてもその経験から学べることもあります。失敗してもやり直しがきく若いうちに、失ってもいい範囲の額で少しずつ資産運用を始めておくのは、いろいろな意味で財産になるともいえそうです。
仕事のスキルを磨くべし!
null
「若いうちに、難易度の高い技量を身につける。歳をとると記憶力が衰えるのでできるだけ若いうちに好きな勉強をしたほうがいい」(63歳男性/その他)
「自分の特技を活かせる国家資格を取得すべき」(66歳男性/その他)
「なるべく興味がある事を勉強してお金に繋がるように準備する」(62歳女性/その他)
老後に困窮しないためには、貯蓄や投資でお金を確保しておく以外に、定年後もずっと働き続けるというのもひとつの考え方。年齢を重ねても社会から必要とされる専門スキルを獲得できるかどうかも、60代までの過ごし方にかかっています。よく言われるように「思い立った日が一番若い日」。「学生時代と比べて記憶力も落ちているし……」など後ろ向きにならず、自分の興味のある分野の勉強を今日から始めてみてはいかがでしょうか。
運動習慣を身につけるべし!
null
「ラジオ体操など持続可能な運動習慣」(73歳男性/営業・販売)
「若いときから運動習慣を身につけて、体力・筋力の維持向上を怠らないこと。私は社会人になってから全く運動をしていませんでした。45歳くらいで膝に違和感が出て“これではいかん”と思いやっと運動を始めました。早めに始めることが肝心だと思います」(60歳男性/その他)
「一番大切なのは健康な体を維持すること。スポーツの習慣があればそれに越したことはありませんが、もし無理なら近くへの買い物は車を使わないなど生活の中に運動を取り入れるべきだと思います」(72歳男性/その他)
年齢を重ねたときの大きなリスクのひとつは、足腰が弱って寝たきりになってしまうこと。それを防ぐために、若いうちから運動習慣を身につけておくべきとの声も多く寄せられています。
高齢になって心身が衰えると、ますます体を動かすのが億劫になりさらに身体機能が低下する……なんて悪循環に陥りがち。わざわざお金をかけたり、ハードな運動を自分に課したりするのではなく、軽くウォーキングをするなど無理のない範囲で体を動かす習慣は、健康寿命を延ばし充実した老後を送るうえで重要かもしれません。
健康維持のためには、こんな心がけも…
null
「栄養バランスに配慮した食事は体の基本。60歳ぐらいになると色々なところに体の不調を覚えるようになりますが、毎日の食事に気を使っていれば、健康的で不調もあまり感じないと思います」(65歳女性/その他)
「できるだけ歯を治しておく」(66歳男性/総務・人事・事務)
「突然、病に伏すことがないように、定期的な健康診断を必ず受けています」(77歳男性/その他)
「骨粗しょう症の予防」(60歳女性/主婦)
健康維持の秘訣として、食生活の改善や健康診断の受診をすすめる声もありました。「そのうちやればいい」「面倒くさい」などを言い訳にして、自分のケアを疎かにすると、何十年後かに後悔することになりかねません。
運動と同様、まずは自分のできる範囲の小さなことから始めてみてはいかがでしょうか?
趣味を見つけるべし!
null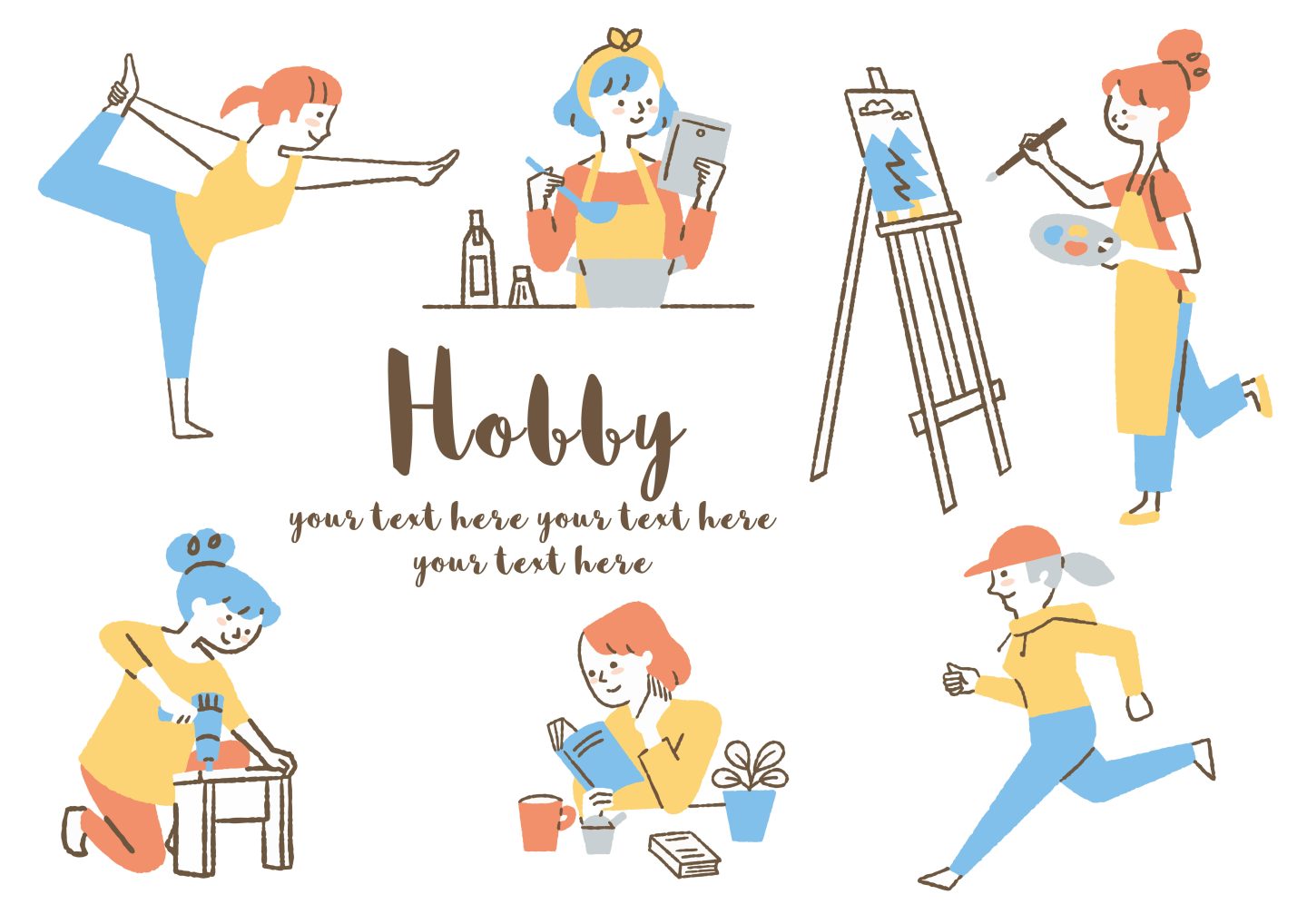
「長く続けられる趣味の確立。趣味があれば大抵の困難があっても乗り越えられる」(69歳男性/総務・人事・事務)
「できるだけ若いうちから没頭できる趣味を見つけ、始めたほうがよいと思います。私の場合は40年ほどになりますが、それでももっと早く始めればよかったという思いがあります。これだけは人後に落ちないと言える趣味を持って老後を迎えられたほうが、より充実した人生を送れるのではないかと思います」(72歳男性/その他)
「趣味を通じた友達作り。老後を友達と楽しく過ごすため」(63歳男性/その他)
「定年後に楽しめる趣味を持つこと。一人で無理なくできる趣味がいいですよ」(65歳男性/公務員)
体だけでなく心も健やかな老後を送るには、生きがいとなるような趣味を見つけておくのも大事。現役世代は仕事や家事、育児に忙しく、なかなか趣味を嗜む余裕もありませんが、かといって、リタイヤ後は気力の問題で新しい趣味を始めたり継続したりするのが難しいという状況もあるようです。
ひとりで没頭できるものでも、仲間とつながりを感じられる団体活動でもお好みで! 一生ものの趣味を見つけておくと、老後の生活が彩り豊かなものとなるでしょう。
人との縁を結ぶべし!
null
「友人作りが大切。私は内向的なのでそれができず、今、孤独感に苛まれています」(66歳男性/総務・人事・事務)
「友人をたくさん作ること。何でも相談できる友人がいれば、不安を軽くするから」(78歳男性/その他)
「地域の自治会とのつながりを作るために自治会の役員などを率先して務めること。そうすれば老後の孤独を防ぐことができる」(82歳男性/その他)
老後の問題のひとつとして挙げられる社会的孤立。その不安を解消するために、若いうちから仕事以外の人とのつながりを持っておくほうがいいとのアドバイスもありました。
たしかに、今ですら人付き合いが苦手な筆者など、高齢になってから社交デビューなんて滅相もない! 夫に先立たれたら身近に頼るつてが皆無でこりゃ確実に詰むな……と戦々恐々です。手遅れになる前に、趣味のサークルや地域の会合など、何らかの形で人と触れ合う機会は持っておかねばと切実に思います。
その他、老後に備えてこんなこともおすすめ!
null
「いわゆる断捨離。モノ、人間関係などのしがらみを大幅に減らしておくと後が楽。歳を取ってからでは何かと身動きがとれないから」(67歳男性/総務・人事・事務)
「近場でも国内でも海外でも、いろいろな所に行きそれぞれの場所の名所・旧跡・風土を知ると、自身の世界観が変わると思います。歳を重ねるにつれ、時間はたくさんあるのに出掛ける気力・体力がだんだん落ちてしまうので」(70歳男性/その他)
「自立心を持つ。頼り切っていた妻が急死して自分も健康を害した」(74歳男性/その他)
「いつ死ぬかわからないので、好きなことをやりなさい」(61歳男性/会社経営・役員)
「先のことはわからないので、今の生活を続ければよしとします」(82歳男性/その他)
身辺整理や海外旅行も納得ですが、筆者的に刺さったのは「いつ死ぬかわからないので好きなことをやっておけ」とのメッセージ。もちろんお金の備えや健康維持も必要だけれど、高齢になってから「若い頃、もっとこうしておけばよかった」と嘆くことがないよう日々、自分の直感を信じて行動することも大切かもしれません。
さすが人生の先輩の発言は重みがある!……と膝を打ってしまったのは、きっと筆者だけではないはず。老後に対して漠然とした不安のある人はぜひご参考にしてみてはいかがでしょうか。

成人までの人生を受験勉強にささげた結果、東京大学文学部卒業。その後なぜか弁護士になりたくて司法試験に挑戦するも、合格に至らないまま撤退。紆余曲折の末、2010年よりフリーライターの看板を掲げています。























