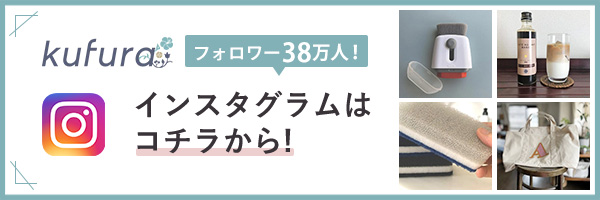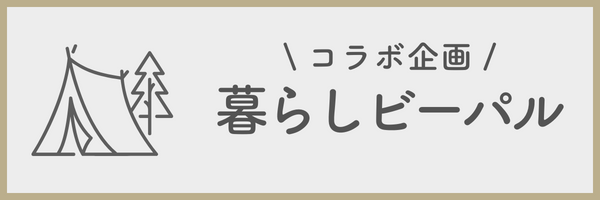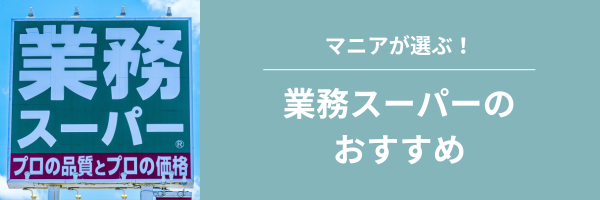両生類を捕獲した場所と違う場所に放すのは、なぜNG?
null
―近年、“SDGs”という言葉とともに“生物多様性”といった言葉が使われています。
テレビ番組などの影響で生物多様性を脅かす“外来種”についての認知は一部で進んでいますが、一方で、国内で捕った水生生物を別の場所に放す“善意の放流”による“国内外来種”も問題になっていると聞きました。
吉川夏彦さん(以下、吉川さん):非常に大きな問題です。
その地域に生息している生物の種類は、地域ごとに異なるからです。例えば日本の中でも本州・四国・九州と沖縄の間では生息しているカエルの種類は全く異なります。
本州と北海道でも同様で、本州の中でも東北と関西では見られる種類が違います。カエル以外の動物や植物でも同様です。もともとその場所にいなかった種類の生物が新たに持ち込まれると生態系に大きな影響を及ぼす可能性があります。
また、たとえ同じ種類の分布の範囲内でも、地域ごとに微妙な違いがあります。
例えば、同じ国内の、同じ種のカエルでも、温暖な地点Aのカエルと、寒冷な地点Bのカエルだったら、暑さや寒さへの耐性や、特定の病気への耐性が異なっている可能性があります。
生息地の環境に合わせて、長い時間をかけて微妙な適応進化を遂げているのです。そうした地域ごとの特性が乱されることは大きな問題です。
別の土地で採集された両生類を逃がすことで、その場所に新しい病原体が持ち込まれる可能性もあります。
おそらく、多くの人は外国から連れてきた、日本にいない生物をその辺りに放すのは“よくないこと”と感覚的にわかっています。でも、国内で捕獲した生物を、その個体が自力で到達できない地域に放流することも、以上のような理由からよくないのです。
本来なら、カエルなどの多くの両生類は移動能力が限られていて、普段の行動範囲はせいぜい数百mから数km程度の範囲です。ましてや自力で海を越えることはありませんから。
―どこか遠くで捕まえたカエルやオタマジャクシを良かれと思って身近なカエルの生息地に放した場合、病気などのダメージをもたらす可能性があるんですね。
今、北海道で起きている「国内外来種」の問題とは…
null―“善意の放流”にも繋がる問題ですが、日本国内では、両生類の人為的な移動が生態系に影響を及ぼしている実例はありますか?
吉川さん:例えば、近年、北海道で“国内外来種”のカエルが問題になっています。
もともと北海道には“ヒキガエル”はいません。本州との間に津軽海峡があるので、本州では普通にみられるカエル類も北海道には何百万年もの間入ることができませんでした。しかし近年になって人為的に持ち込まれたことで、在来種をおびやかすようになりました。
北海道には固有種の両生類であるエゾアカガエル、エゾサンショウウオなどが生息しているのですが、それらがヒキガエルの卵やオタマジャクシを食べるとその毒で死んでしまいます。言ってみれば、彼らの進化の歴史の中で出会ったことのない毒生物が突然現れ、対処できずに死んでしまっている状況です。
一方、ヒキガエルは、ライバルの両生類が減り、さらに増えてしまいます。
―固有種が大きなダメージを受けることで、“生物多様性”が失われていくんですね。
そもそも、生物多様性はなぜ大事なのか?
null
―なにげなく“生物多様性”という言葉を使ってしまったのですが、そもそもなぜ生物多様性の重要性が叫ばれているのでしょうか。
吉川さん:生物多様性とは、基本的に、人間視点の言葉です。
地球上の生物は、人間にとっての資源としてみた場合、すでにその価値がわかっていて日々の生活に直接的・間接的に利用されているものと、そうでないもの(利用価値があるのかわからないが、これからの研究や技術開発などで価値が出てくる可能性を秘めたもの)があります。
生物資源として利用されている生物は、生物種全体としてはわずかですが、「人類の持続的な発展のために今後活用できる可能性を踏まえて、できるだけ多様な生物を残しておくほうがいい」という視点が含まれています。
私個人として、生物を経済的な価値に置き換えることには思うところはあるにせよ、そういう視点はとても重要です。
―持続可能な人間社会を維持するためにも、環境や生態系を守らなければならない、と。
吉川さん:例えば、新型コロナウイルスの検査などで有名になったPCR検査に使われる試薬の1つである耐熱性DNA合成酵素は、もともと温泉や熱水噴出孔の付近で発見された耐熱性の細菌がもつ酵素を人工的に合成したものです。いまではいろんな細菌から同様の酵素が見出され、改良を加えて様々な検査や研究に利用されています。
1つの例ではありますが、私たちの身の回りで活用されている物質は、自然由来のものやそれをもとに開発されたものが圧倒的に多いのです。ゆえに、現在も国内外の企業や研究機関は、自然界のさまざまな物質を収集しています。
―自然界で発見された酵素がPCR検査を支えていたとは……。
吉川さん:ちょっと話はそれましたが、もしかしたら、両生類だって何かの種や、どこかの地域の固有種が、いつか役に立つ成分やメカニズム、遺伝子を持っているかもしれないし、あるいは、生物の進化を理解するための学びに役立つかもしれません。個人的に「役に立つか、立たないか」という考え方は好きではないのですが、そういう側面もある、ということです。

国立科学博物館 筑波研究施設から見える筑波山。新種として発見された国内希少種の「ツクバハコネサンショウウオ」が生息する。
―ある土地で長い時間をかけて育まれた特性が、いつかどこかで役に立つ“かもしれない”んですね。
吉川さん:そうですね。両生類に関して言えば、移動能力が低いこともあり、他の地域の集団との交流が限られていて、何万年もの時間の経過とともにその土地ごとの外見や遺伝的な違いが生じていきます。それを“地理的変異”といいます。
私は、両生類のサンショウウオの遺伝子を調査していますが、生息地によって、さまざまな違いがあるんですよ。たとえ同じ種に分類されていても、遺伝子を調査すると、地域ごとに特有の変異をしていることがわかります。
―生物多様性は、地域ごとの変異の歴史をも包括している奥の深い言葉だということがわかりました。
【取材後記】
今回お話をうかがった吉川さんは、日本の“普通種”とされていた両生類の「ハコネサンショウウオ」が、複数の種に分類できることを研究を通じて発見しました。この件について国立科学博物館は「よく知られた身近な種であっても未知の多様性を秘めていることの好例」とコメントしています。
たとえ同じ種でも、ある地点の生物と、別の地点の生物は、地域ごとに独自の変異をしている可能性があり、多様性を秘めているかもしれない、ということを頭の片隅に置いておきたい、と感じました。

【取材協力】
吉川夏彦
国立科学博物館 動物研究部 脊椎動物研究グループ 研究員。
サンショウウオやカエルなどの両生類を主な対象として、種の分類や種内の地域変異の解明、その成り立ちについて研究を進めている。サンショウウオ類の生態調査や保全に関する研究にも取り組む。
最近は水田のカエルの研究のため全国の田んぼを歩き回っている。
2022年にはハコネサンショウウオ属というグループの新種で日本固有種の「ホムラハコネサンショウウオ」を発見。
『国立科学博物館』ホームページ:https://www.kahaku.go.jp/index.php