鉄ってなぜ必要なの?
nullこんにちは、管理栄養士の宮崎 奈津季です。最近「鉄分不足」「鉄分補給サプリ」などの広告や話題をよく見る気がしませんか? 意外と知らない「鉄分(以下鉄)」について解説します。
鉄は常に不足気味!
鉄は体内に3~4gほど含まれているミネラルの一つです。そのうち、約70%は血液に、約4%は筋肉に、残りは肝臓や脾臓、骨髄にあります。
体内で効率よくリサイクルされており、排泄される量は1日あたり1mgほどといわれています。その分だけ補給すればよいと考えるかもしれませんが、鉄は吸収率が低いため、その何倍もの量を食事から摂る必要があるというのがポイントです。
日本人の食事摂取基準(2020年版)における30~49歳の女性(月経あり)の場合では、推定平均必要量(半数の人が必要量を満たす量)が9.0mg、推奨量(ほとんどの人が充足している量)が10.5mgとなっています。
しかし、令和元年国民健康・栄養調査報告によると、鉄の平均摂取量は、30代で6.4mg、40代で6.7mg。推定平均必要量に届いていないのが現状です。
鉄はどんな働きをするの?
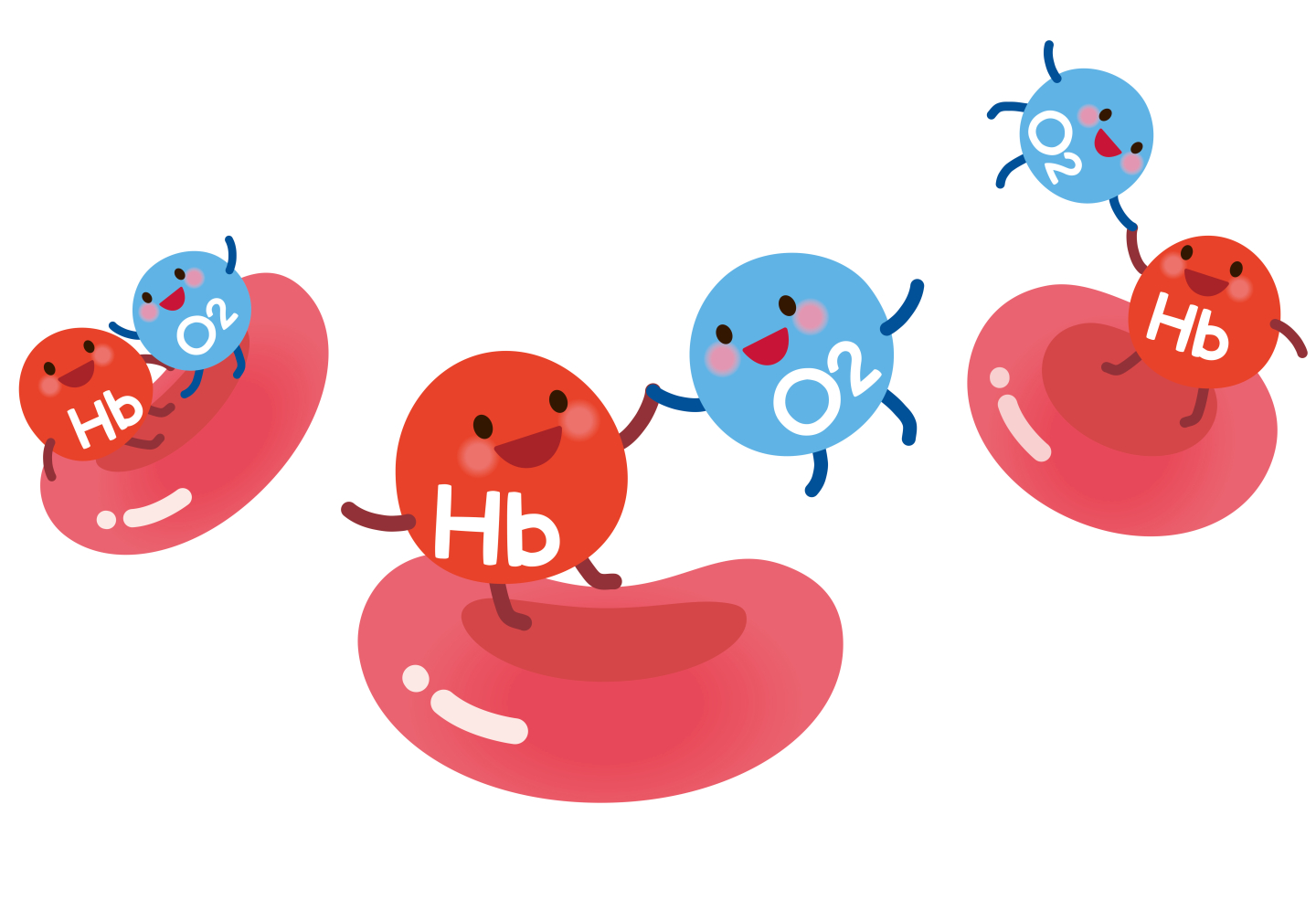
赤血球の中で、ヘモグロビン(Hb)の中の鉄が酸素(O2)と結びついて全身に運ばれる。
鉄は、赤血球中のヘモグロビンと呼ばれる成分の材料となっています。ヘモグロビンの働きは、酸素と結びつき、肺で酸素を取り込んで全身の細胞に送り届けることです。また、鉄はそれ以外にもミオグロビンという成分の材料となり、血液中の酸素を筋肉に取り込む役割があります。それ以外にも体内のエネルギー産生に関わっています。
鉄が不足したらどうなる?
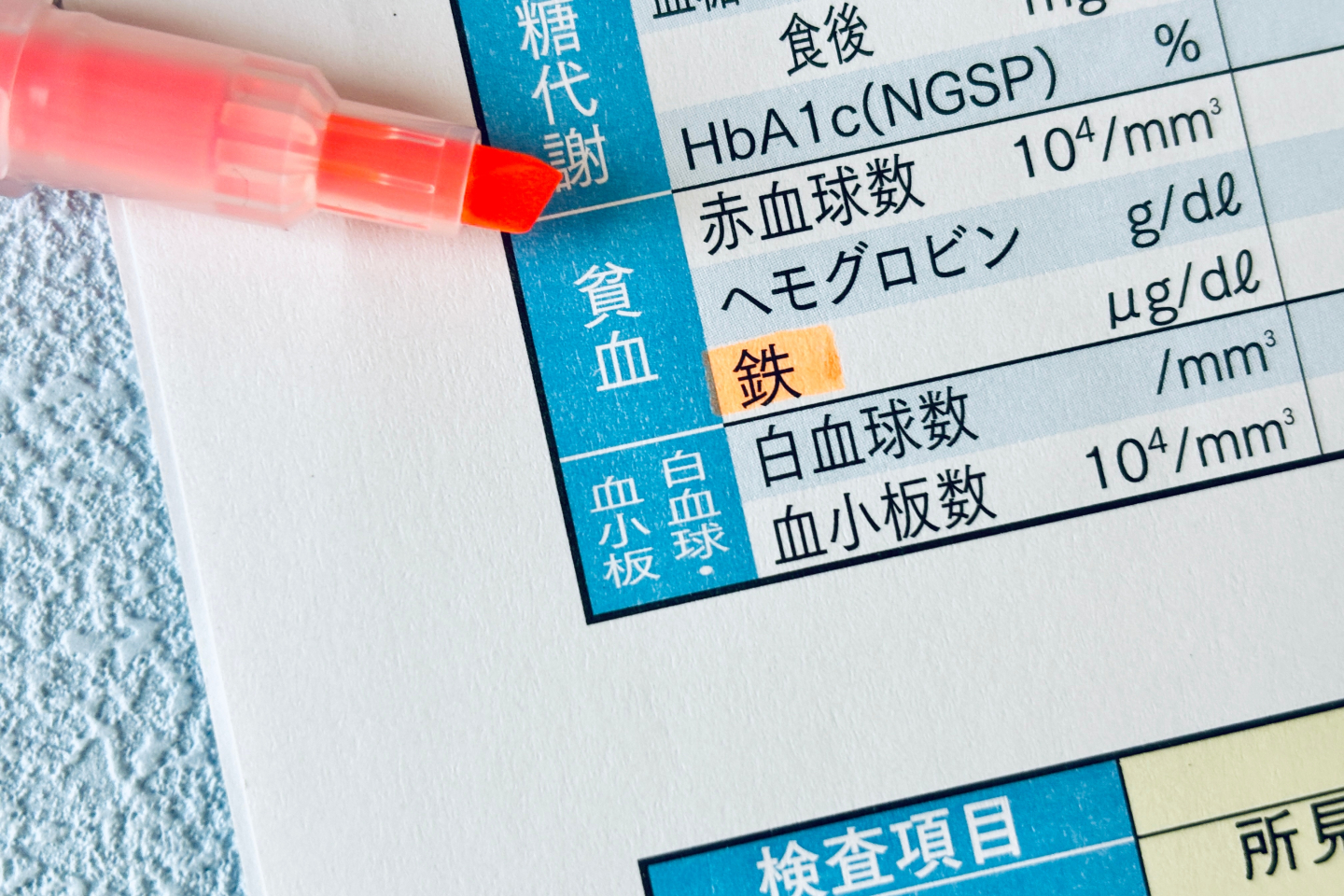
鉄の欠乏症は、「鉄欠乏性貧血」です。症状としては、疲れやすくなったり、頭痛や動悸、息切れなどです。また、過多月経や子宮筋腫などで出血症状がある場合は、不足しやすくなります。
鉄には酸素を利用するために働いている「機能鉄」と、機能鉄が不足する際に補給する役割のある「貯蔵鉄(フェリチン)」の2種類があります。基本的に、機能鉄が不足すると、貯蔵鉄が血液中に放出されますが、この貯蔵鉄が底をつくと貧血が起こります。
その前段階として、なんとか機能鉄を維持しようと貯蔵鉄を利用することで、貯蔵鉄が不足している状態を「かくれ貧血」と呼ぶことがあります。疲れやすさやだるさ、めまいなどの症状が出ることもあり、不調を感じる方も。体調不良を感じていたら鉄不足のせいだった、ということもあるかもしれません。
鉄はどう摂ればいい?
nullヘム鉄・非ヘム鉄の違い
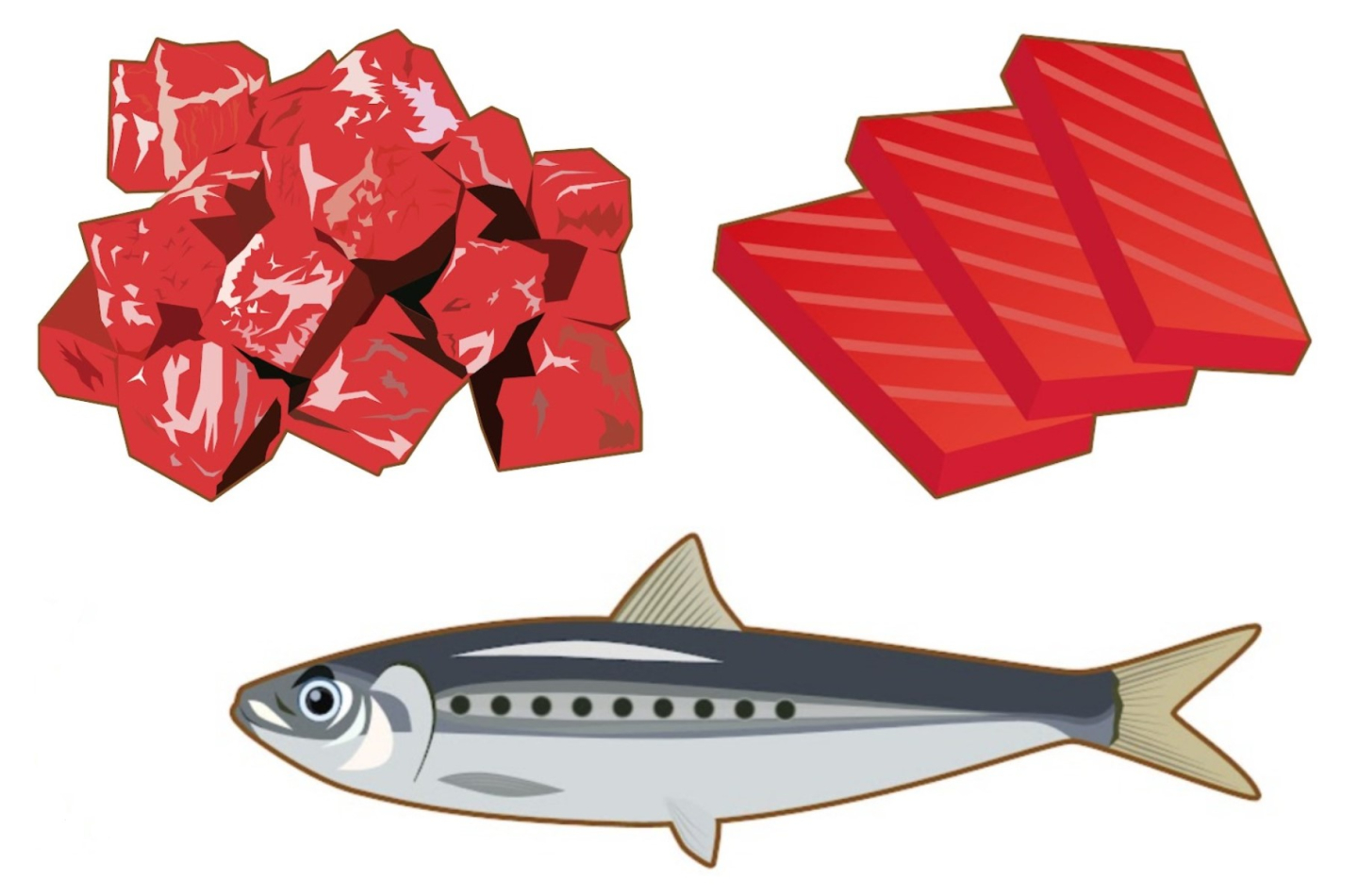
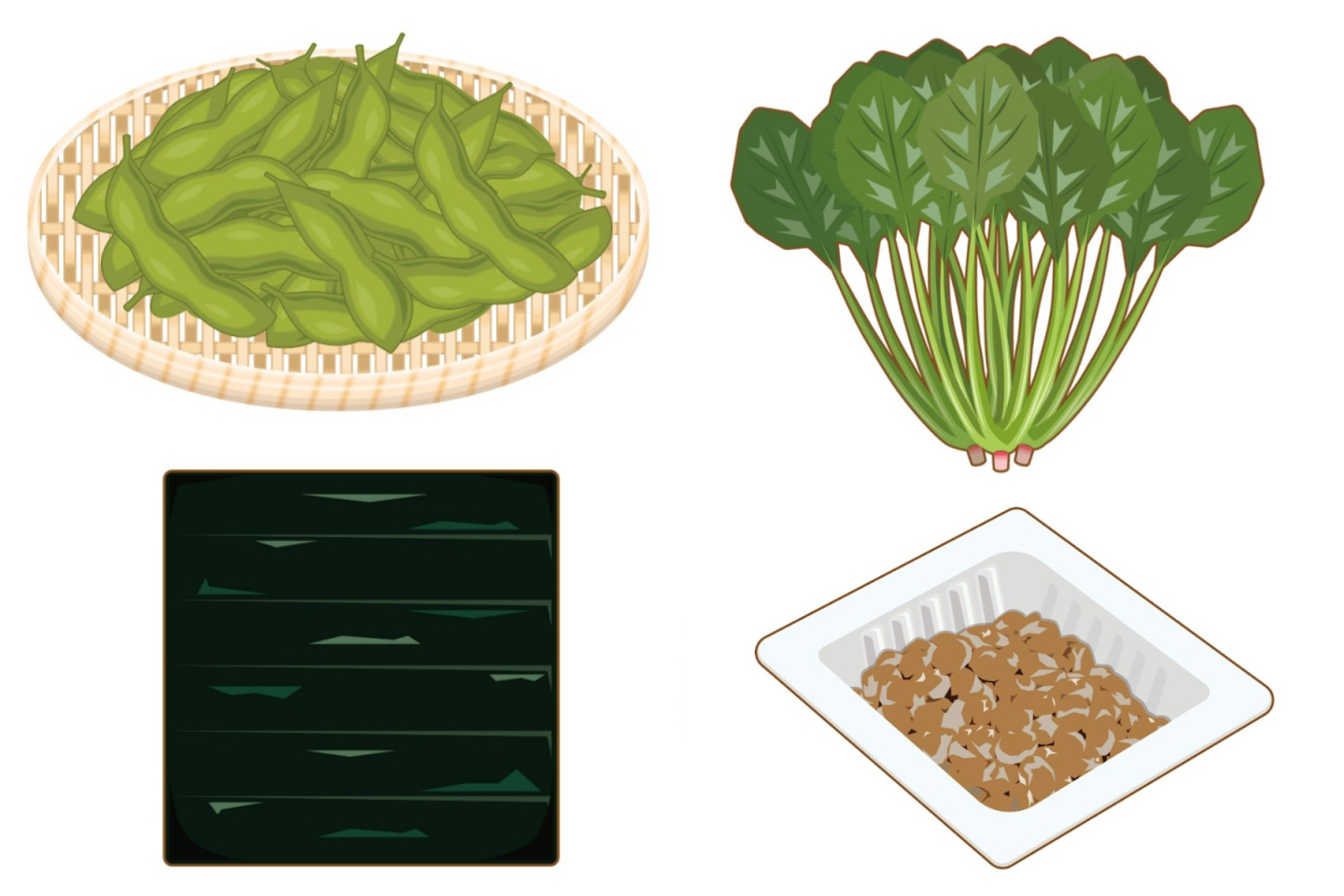
鉄には2つの種類があり、吸収されやすさが異なります。植物性食品に含まれる鉄は「非ヘム鉄」と呼ばれ、動物性食品に含まれる鉄は「ヘム鉄」と呼ばれています。非ヘム鉄よりもヘム鉄のほうが吸収されやすいことがわかっています。また、ヘム鉄を利用することで、非ヘム鉄の吸収もよくなります。
吸収率の違い
鉄の吸収率は、食事から摂取したヘム鉄と非ヘム鉄の構成割合や吸収を妨げる栄養素や食品、鉄の必要状態によって異なります。日本人の食事摂取基準(2020年版)では、諸外国の報告を参考にし、妊婦を除き吸収率を15%として、それぞれの摂取基準の量を算出しています。
レバー以外にも!鉄が多く含まれる食品

鉄はおもに動物性食品に含まれています。中でも、鉄が貯蔵されているレバー(肝臓)類は、かなり多く含まれています。それ以外にも、赤身の肉にも豊富です。魚介類では、しじみやあさりなどの貝類、魚では赤身のかつおやまぐろに多く含まれます。
植物性食品では、のりなどの一部の海藻類にも多く、乾物なら少量でも鉄が摂れるので、摂取源として重宝します。野菜では大根の葉や小松菜、大豆製品では納豆や湯葉にも含まれています。
吸収率を上げるには?
鉄はビタミンCを一緒に摂ると吸収を助けてくれます。例えば、レモンやオレンジなどの果物、さつまいもやじゃがいもなどのいも類です。野菜では、ピーマンやブロッコリーなどに多く含まれています。
逆に鉄の吸収を妨げるものとして、食物繊維、豆類に多く含まれるフィチン酸、コーヒーや緑茶に多いタンニンという成分が知られています。しかし、これらは身体によい働きもあるので、摂りすぎに注意する程度で大丈夫。「一緒に食べてはいけない!」というものではありません。
【参考文献】
・上西一弘:「栄養素の通になる第5版、女子栄養大学出版部」(2022)
・飯田薫子・寺本あい:「一生役立つ きちんとわかる栄養学」西東社(2019)
・厚生労働省:「鉄」e-ヘルスネット
https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/dictionary/food/ye-022.html(閲覧日:2024年5月24日)
・厚生労働省:「令和元年国民健康・栄養調査報告」厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/eiyou/r1-houkoku_00002.html(閲覧日:2024年5月24日)
・厚生労働省:「働く女性の心とからだの応援サイト」
https://www.bosei-navi.mhlw.go.jp/(閲覧日:2024年5月24日)
























