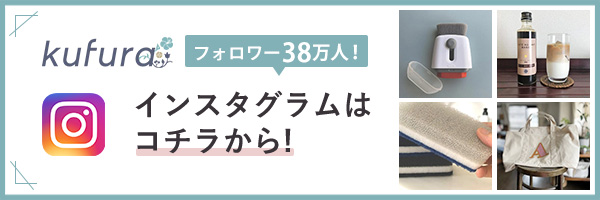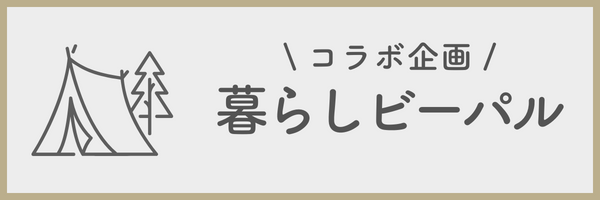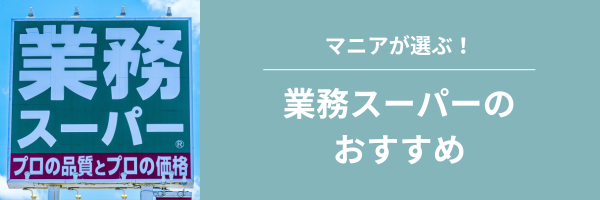数日の入院で勉強は必要なのか?
null副島先生の第一の難関は、医療スタッフとの間に隔たった考え方があることでした。12年前は、今のように教育が子どもにとって欠かせないもので、病気の予後に良いのではないかという見方もなく、治療を最優先する医療者との対立があったのです。
たった3、4日の短い入院ならば、何も勉強しなくてもいいじゃないか、という声が圧倒的だったといいます。
「勉強や学習という言葉を使うと反発があるので、発達という言葉を使うようにしました。“子どもにとって生きることは学ぶことです。普段のように教室に通うことで、発達や病気の回復にも必ず役立つはずです”と。
最初はナースセンターにも入れませんでした。何かご用ですか?と言われて……(笑い)。しかし、僕の思いを説いて回り、最初の年は病棟保育士、次の年は看護師、そして医師と徐々に応援を取り付け、3年目には医療カルテを見せてくれるまで信頼関係を築くことができたのです」
そうするうちにナースセンターに顔を出して子どもの状態を聞き、必要があれば手術前のカンファレンスにも参加して、子どもの表情を読み取ることのできる機会を与えられたそうです。集中治療室にいる子にも会いに行き励ますと、苦しいながらも笑顔で返してくれる子どももいたといいます。
長年の積み重ねの結果、今では、病院側は授業と治療の時間が重ならないように考慮してもらうまでになったそうです。

さいかち学級に飾られた子どもたちの作品。
先生は、きみたちを比べたりしないよ
null医療スタッフとの連携に心を砕くとともに、副島先生は子どもたちの病室を回り、「先生の許可が出たら、病棟の上にある教室に遊びに来てね」と、赤鼻をつけて“顔を売り”ました。「行ってみたい」と思ってもらえるように、なんとか院内学級への敷居を低くしようと足しげく通ったのです。
さいかち学級にやってくる子どもたちがまず決まってするのは、他の子を傷つけることだといいます。他の子に「まだそんなことやってるの?」「僕はもうできるよ」と、自分のほうが優位に立つことを明言するそうです。
「病気の子どもは、これから自分の居場所がなくなってしまうのではないかと不安なんです。その不安の裏返しで他の子を傷つけてしまう。けっして悪気があるわけではないのです。
だから僕は、このおじさんは安全だから安心して。誰のことも傷つけないし、他の子とは比べないよと、その子が分かる方法で伝えます。その子が好きな漫画やパズルをしながら、短時間のうちに、信頼関係を築くようにするのです」
教室に来るようになった子どもたちの次の問題は“勉強”です。たとえ教室には来ても「勉強はやりたくない、やらないよ」という子がたくさんいるそうです。副島先生は、この子にはきっとやりたくない理由があるだろうと思って丁寧にかかわります。
「僕は4年生なのに、3年生の問題も分からないんだよ」
「あの子は2年生なのに、九九がスラスラいえる。でも僕は6年生なのに、掛け算ができないんだよ」
そんな思いを抱えていました。
「子どもたちは、できない自分に出会って、愕然としているわけです。大人だって、できないことをできないと認めるのは簡単ではありません。これまでずっと、ひっかかりがあったのでしょう。それを正直に認めることは勇気のいることです。
だから僕は言うんです。できなかったことも間違ったことも自分の口で言えたんだから、すごいよ。1年生の勉強からやればいいんだよ。大丈夫すぐにわかるようになるよ、と」
病気になった子は傷ついている
null勉強をやらない子には、ほかにも理由がありました。
「手術が怖いから、勉強のことなんて考えられないよ」
「お父さんとお母さんがけんかをしている。僕のことが原因かもしれない。そんなときに勉強なんて手につかないよ」
「子どもたちは自分が怪我や病気になったことは、迷惑かけた、失敗した、と思っています。自分が失敗して周囲に迷惑をかけている子どもたちに、勉強しなさいというのは無理。一人で傷つき、誰かに“助けて”と言えないのです。
まずは勉強よりも先に、助けてと言ってもいいんだよ。助けてと頼める大人もいるんだよ。ということを理解できるように、ターゲットを決めて独自のプログラムを作るのです。
そのためには、国語という教科を使うのがいいのか、算数がいいのか。工作で作品を作るのがいいのか、頭をひねりますね。時間割通りの授業もしますが、実はこちらにはもうひとつの意図もあります。子ども達が未来を感じられるようにしたいのです」
さいかち学級の工作が並べられた台には、フエルトで作られたお寿司がありました(下写真)。きっとこれは「退院したら思いっきりお寿司が食べたい」という気持ちの表れだったのかもしれません。

自己肯定感をもてるように
null病気になった自分はダメだと思っている子どもたちに必要なのは、自己肯定感だと副島先生は言います。
「自分は自分のままでいい。キミはそのままで大切な存在なんだよ」というメッセージを先生は投げ続けています。
「僕は教育者なので教育を使って自分が肯定的なイメージを持てるようにします。医療者は体を回復させたり、心理士さんは心理のことをやったり、保護者の方は保護者ができることをやります。
そういう中で、自分は大事なんだなあと思えるようになることを応援している。病気の子には教育が必要なんです、という使命でやっています。
今、学校でいう自己肯定感は、半分なんです。勉強が“できる、分かる”ばかりで自信をつけさせるんですが、それでは中途半端。自分が大事だとか、自分のままでいいんだと思えない子に“できる、分かる”ばかりを突きつけてダメです。
子どもは裏を読んで、できなければ自分は愛されないんじゃないか、と思ってしまう。失敗してもできなくても、あなたは愛されてるんだよ、そういう気持ちを持たせないといけない。
病気があってもなくても、愛されているんだよ。と思えることが大事だと思います」
さいかちにやってくる子は、才能をたくさん持っています。小学校4年生だった女の子は、詩の才能にあふれていました。副島先生が彼女の詩をほめると、嬉しそうに笑います。そして言いました。
「もし大人になれたら詩人になるんだ」
その「もし」に込められた彼女の思い。その重さの意味を副島先生は改めて実感したそうです。(第3回に続きます)
【取材協力】
副島賢和(そえじままさかず)
1966年、福岡県生まれ。都留文科大学卒業後、東京都の公立小学校の教師に。2001年、東京学芸大学大学院修了。2006年より、『さいかち学級』の担任。14年から現職として『さいかち学級』のアドバイザーを務めている。著書に『あかはなそえじ先生のひとりじゃないよ ぼくが院内学級の教師として学んだこと』(学研教育みらい)。