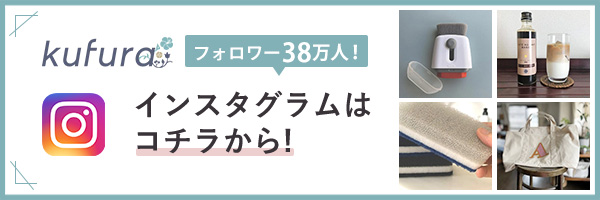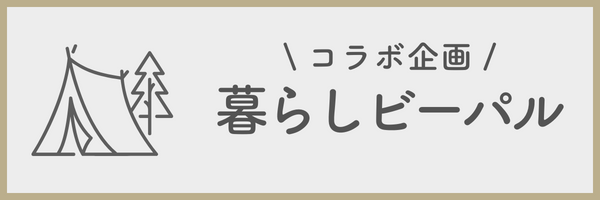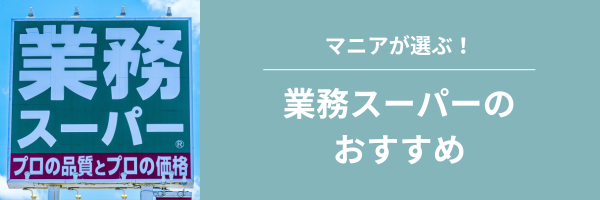連載を書籍にするにあたっては…
nullこの連載「ママはキミと一緒にオトナになる」の書籍化の話をいただき、打ち合わせに行ってきた。担当の編集者さんと対面で打ち合わせするのは、2年ぶりだ。というか、この連載の依頼をいただいたときぶりだ。この連載は、すっぽり、コロナの時期に重なっている。
カバーやタイトルはどうするか、何ページくらいにするか、ラストはどんなふうに終わるのか。 いろんなアイデアを出しては転がし検討していたら、あっという間に1時間半たっていた。オンラインではなかなか、こうはいかない。やっぱり、ブレストはリアルに限りますね、なんて会話もした。
さて、いろんなことを話し合ってきたけれど、この連載の書籍化に関して、一番話し合わなくてはならない相手は、家にいる。
息子氏だ。
「ひとまず、彼と相談して、またご連絡します」
と伝えた私に、
「そうしてください。息子さんが出してほしくないという記事は、出さないことにしましょう」
と、編集さんは言ってくださる。
そういえば、連載のご依頼をいただいたときも、「息子と相談してからでいいですか」と言った私に、「もちろん、そうしてください」と言ってくれたことを、思い出した。
子どもについて書き残しておく、ということ
連載が始まったとき、息子は小学3年生だった。
2年前、私はこの連載についてなるべく丁寧に説明したつもりだったけれど、彼は「うん、好きにすれば」と、あまり興味を持たなかった。まあ、そうだよね、まだよくわからないよね。「嫌だなと思うことがあったら、いつでも言って」と伝えたが、その言葉が彼の耳に届いていたかどうかはあやしい。
実際に書き始めたら、これはなんだか遺言のようだなと思った。
ちょうど離婚したばかりだったせいもある。
父親が一緒に暮らしていたら、私に何かあったとき「ママはよく、こんなことを言っていたよ」と伝えてもらえるだろう。でも、息子と2人暮らしで私が死んだら、私が普段彼をどんなふうに見ていたか、愛していたか、伝えてくれる人はいない。
だから、遺言みたいだなと思いながら、書いてきた。彼がこの文章を読むことがあるとしたら、私が死んだときか、彼に子どもができたときか。
なんとなく、そう思っていた。
父が亡くなったこともある。
父は生前、私や弟について書いた文章をときどき公開していた。子どもの頃、私はその文章をこっそり読むのが好きだった。
教員だった父は普段、私たちきょうだいに対して、ことさら厳しい態度をとっていた。子ども時代に褒められた記憶なんて、ほとんどない。
でも、父が書く文章の中には、ときどき「ああ、この人は、本当は私たちのことを気にかけてくれているのだ」と確信を持てる表現があった。それに触れたくて、父の文章を読んでいたのだ。
お葬式のとき、「お父さんの文章で、ゆみちゃんのことをよく知っていた気持ちになっています」と言ってくれた人が何人もいた。
そのときやっぱり、子どもについて書き残しておくことは、遺言みたいだなと思った。
「ねぇ、今のも、書くの?」
連載が始まってしばらくたつと、息子が「最近ママは、優しくなったね。僕の言うことをよく聞いてくれる」と、言うようになった。
たしかにそうかもしれない。この原稿を書くようになってから、彼の言葉を上の空で聞き流すことが、少なくなった。
このころ私は、この連載、一石二鳥、いや一石三鳥かもしれないと思っていた。
私は子どものことをもっと深く知ろうとできる。子どもは私に、しっかり話を聞いてもらえていると感じる。そして、それが仕事にもなっている。
記事が公開されるたびに、いろんな感想をいただいた。
ご自身の子育て体験を教えてくださる方もいたし、自分が子どもの頃の話をしてくれた人もいた。私はいつも結論のない話を書くから、いろんな議論が生まれた回もあった。
いろんな人たちが自分の子どもや、子ども時代の自分を、優しく見つめ直している様子が知れるのも、とても嬉しかった。
と、そんなこんなで、ささやかに調子に乗った私が、頭をガツンと殴られたのは、息子が4年生のときだったか。
息子の言葉が聞き取れなかったので
「ん? 今、何て言った?」
と聞き直したら、
「ねえ、今のも、書くの?」
と、息子がうんざりした顔をしたのだ。
「ねえママ、書かれるかもしれないと思うと、僕、安心してママと話ができないんだけれど」 と言われて、ハッとした。
あ、これはもう書いちゃダメだ。そう思った。
これは「ママがどう考えたか」ってことだから
「ごめん、ママがキミのこと書くの、嫌だった?」
と聞くと
「うーん、それはいいよと言ったけれど、どこまで書いているのか気になってきた」
と言う。
「わかった。じゃあ、ママもう、書くのやめるね。ママは、キミのことをもっとわかりたいと思って書いている。だけど、これを書くことで、キミがママと話しにくくなるなら、それは本末転倒だと思うから」
「でも、この仕事やめたら困らない?」
「仕事よりも、キミとの関係の方が大事だと思う。編集さんにも、そう伝えるね」
そう言って、その日はそのまま床についたのだけれど、次の日になって彼は、私に話しかけてきた。
「昨日の話だけど、やっぱり、やめなくていい。書くのをやめてほしいわけじゃないんだよね」
と、言う。
「我慢しないでほしい。気になるんだよね?」
と聞くと、
「一度、読ませて」
と言うので、そのとき書いていた原稿を彼のケータイにLINEした。
彼はしばらくそれを読んでいたようだけど、
「うん、やっぱりママの好きに書いていいや」
と言ってきた。
驚いて、本当にいいの?と聞くと、大丈夫だと言う。これからも今日みたいに原稿チェックする?と尋ねたら、それもしなくて良いと言う。
「これは、ママがどう考えたかってことだから。僕の考えと違ってもいいと思うし、もし誰かに何か聞かれたら、『ああ、あれはお母さんがそう思ったということなんですよ』って言うからいい」
彼が、4年生の時のことだ。
その後も何度か、提出する前に読む?と聞いてみたが、そのたびに「いや、べつにいい」と言われることが続いた。
「ママ、死なないでよ」
書籍化の可能性がある話は、前から伝えてあった。
彼にとって、ウェブと書籍はちょっと意味が違うらしく、本が出るときは教えてほしいと言われていたので、私は打ち合わせのあと、彼に話をした。
「今日、ドラえもんとコナンを作った出版社に行ってきたんだけど」
「え、ドラえもんとコナンって、同じ会社なの?」
「うん、そう。あと妖怪ウォッチとか。でね、その会社から、キミのことを書いた本を出そうと言ってもらっているのだれど……」
「え? マジで? そんな有名な会社から本が出て、僕が超有名になっちゃったらどうするの?」
「いや、エッセイって漫画みたいには売れないから、そこは多分大丈夫」
「あと、僕、イケメンじゃないけど」
「いや、キミの名前や顔写真は出ないから、それは大丈夫」
「そうなんだ、じゃあ、頑張って」
「あ、聞きたかったのはそういうことじゃなくて」
なんだか、噛み合わないまま会話が終わりそうだったので、私は慌てて話を続ける。
「本に出す原稿を、読んでチェックしてほしいんだけど」
「ああ、それは、だから好きに選んでいいよ」
「うーん、できれば、キミが納得した原稿だけ出したいんだけど」
「僕がチェックするとつまらなくなるんじゃないかな」
「そっか。わかった。もしよかったら、いつか大人になったときにでも読んで」
と言ったら、ふと、息子がつぶやいた。
「ママ、死なないでよ」
と。
「え?」
と聞き返すと
「死んだときに、ママはこんなふうに僕のことを思ってくれていたんだとか、読むの、絶対悲しすぎて嫌だから」
と、言う。
「うん、でもまあ、いつか死ぬし、死んだときは読んでほしいと思うけれど」
と答えると
「多分、辛くて読めないと思うから、死なないでほしい」
と言う。
遺言だと思って書いているんだけどな、と考えながら私は、
「あ、じゃあ、もしもキミに子どもができたら、そのときに読んでくれたら嬉しいかも」
と言い直した。
「うん、それは、わかった」
と、彼は言う。
3年生から5年生になった彼。すらりと伸びた手足だけではなく、彼はこの2年でとても大きくなった。
母親9歳から11歳になった私。私も、この期間に、一緒に大きくなった。
6年生になる前には、1冊にまとめましょうと編集さんと話をした。
彼のことを、こうやって書いていくのも、もうあと少しか。
そう思ったら、ちょっと寂しい。
画・中田いくみ タイトルデザイン・安達茉莉
◼︎連載・第46回は6月12日(日)に公開予定です
佐藤友美(さとゆみ)
ライター・コラムニスト。1976年北海道知床半島生まれ。テレビ制作会社のADを経てファッション誌でヘアスタイル専門ライターとして活動したのち、書籍ライターに転向。現在は、様々な媒体にエッセイやコラムを執筆する。 著書に8万部を突破した『女の運命は髪で変わる』など。理想の男性は冴羽獠。理想の母親はムーミンのママ。小学5年生の息子と暮らすシングルマザー。