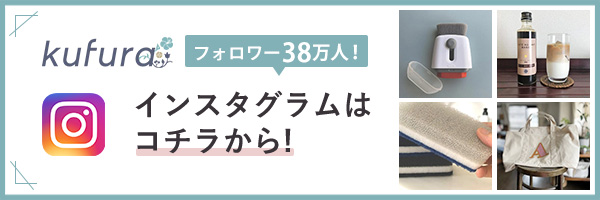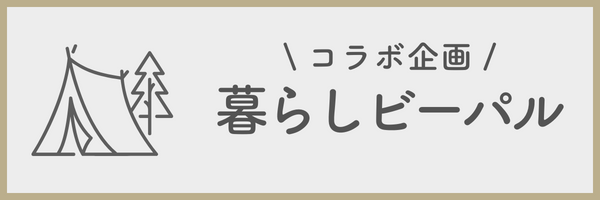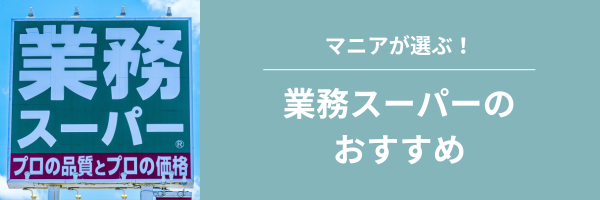救急車で、運ばれた
null年末のこと。クリスマスの朝に、救急車で病院に運ばれた(息子氏ではなく、私が)。
その日、私は、北海道の実家に帰省していた。息子だけを北海道に残し、私は仕事をおさめるために翌朝東京にとんぼ帰りする予定だった。
が、実家に着いて夜寝ようと思ったら、全身に蕁麻疹が出ているのに気づいた。顔も赤くなって熱を帯びている。その時は、何か悪いものでも食べたかなあ。一晩寝たら治るかなあなどと思って、床についた。念のため、東京の皮膚科の予約を入れた。明日、戻ったら速攻で病院行こうと思いながら。
翌朝、
「ばあばの家でも、ちゃんとサンタがきたー!」
という、息子の声で目が覚めた。
彼は、クリスマスを自宅ではなく、おばあちゃんの家で過ごすことを心配していたのだけれど(サンタさん、ばあばの家、わかるかなあ)、どうやらちゃんと枕元にプレゼントがあったらしい。
「おお、よかったねえ」と言って起き上がろうとしたら、目がうまくあかない。鏡を見たら、顔が試合後のボクサーくらいに腫れ上がっていた。呼吸もなんだか苦しい気がする。
「ママ、顔がカチコチだし、すごく熱いよ」
肌に触れた、息子が言う。
フライトの時間が迫っていたけれど、直感的に「これ、飛行機に乗ったらヤバいやつでは?」と思った。救急車を呼んでほしいと母に話す。頭によぎった単語は“アナフィラキシー”だった。かつて友人がそれで大変な目にあったことを投稿していたのだけれど、そのときの話を思い出す。いろいろ、似ている気がする。
息子に留守番を頼んで、救急車に乗った。母も同乗する。
担架で運ばれるとき、息子は一瞬「大丈夫?」と私をのぞきこんだものの、日頃からよく倒れる親に慣れているせいか、それほど心配している様子はない。慣れってすごいな。これが今生の別れになったらどうするんだよ。
そんな私も、しかし意識ははっきりしていたので「まあ、死にはしないだろう」と思って運ばれた。
受け入れてくれる病院を見つけるのに少し時間がかかった。あとから母に聞くと、救急車の中で一度、酸素飽和度がずいぶん落ちたらしい。酸素マスクをつけてもらうシーンもあったけれど、病院についてステロイドをガンガン点滴してもらったら、あっというまに落ち着いてきた。
「フライトしていたら、危なかったですね。でも、もう大丈夫ですよ」
と、若い女性の先生が言う。
先ほど、廊下で
「すみません、急患が入りまして、お迎えが遅れます」
と電話をしていた先生だ。保育園にお子さんを預けているのだろうか。
「私のせいで残業になっちゃいましたよね、ごめんなさい」
と言うと、
「あ! 聞こえちゃってましたか、いえいえ全然気にしないでください。大人の事情で、受け入れが遅れてごめんなさいね」
と言われた。大人の事情って、私よりひとまわりほど若い先生が言うのが面白い。
私が処置をされている間、実家の周りでは、スクランブル態勢が敷かれていたらしい。さすが田舎だ。救急車の到着が秒の速さでコミュニティに伝わり、「どうやら、帰省してきたゆみちゃんが運ばれたらしい」となって、留守番をしていた息子は親戚の家に保護された。
母が暮らす地域のコミュニティが、あたたかく密な繋がりを持っていることに安心したりもした。
症状も落ち着き、予定よりは遅れたけれど、夜には東京に戻ることができた。
息子は、「じゃ、良いお年を」と、相変わらずクールである。
私は、私のために頑張れるのだろうか
この年末年始、私は生まれてはじめて、一人で年を越した。
集中して一気に仕上げたい原稿があったせいもある。でもそれ以上に、「ここらで一度、ちゃんと一人を味わっておきたい」という気持ちがむくむくとわいたのだ。
春を迎えたら、息子は5年生になる。
子どもが生まれたとき、一番早く手離すことになるとしたら、小学校卒業のタイミングだろうと思っていた。
今のところ、寮のある中学校に入る可能性は低そうだから、次は中学卒業のタイミングか。こちらはわりとありそうな気がする。
そう考えると、彼と同じ家で過ごす時間も、あと5年。長くて8年。これまで10年間一緒だったから、その時間よりは短い。
彼がいなくなったら、私の生活はどうなるのだろう。どんな気持ちで料理を作り、どんな気持ちで部屋を掃除するのだろう。
小学1年生の通知表に「人の世話ばかりしていないで、自分のこともちゃんとやりましょう」と書かれた私である。実家を出てからこれまでの人生、なんだかんだと、人の飯ばかり炊いてきた。
妻でもなく、母でもない。そうなったとき、私は、私のために頑張れるんだろうか。私は、私のために生活を整えていけるのだろうか。
それを今のうちにシミュレーションしておきたかったのだ。何か不安を感じるようなことがあったら、“ほんとうに”彼が家を出ていく前に、何らかの対策をとりたいと思ったからだ。
幸い、母が冬休みの間じゅう、預かってくれるという。その言葉に甘えて、ひとり静かな年末を東京で過ごした。
アナフィラキシーになったことで、忘年会も新年会も全部キャンセルした。しばらく蕁麻疹が消えなかったので、メイクもせず、ついでにお酒も控えてみた。
本当に久しぶりに、一人の時間を過ごした。
消えていくもの、残るもの。
薬を飲むと朦朧とする時間をなんとかやりくりし、原稿を書いたり、慌ただしくて普段は掃除できない場所を整理したりした。
昔のノートが出てきて、過去の取材メモや、当時読んでいた本の感想などを見つけた。今後の人生に対する抱負のようなものが書かれているページもある。
どれもこれも、すっかり忘れてしまっていたことばかりだ。
そのときどき、なぎ倒すように人生を走り続けてきた。そうやって過ごしてきた時間のほとんどは、降りはじめの雪のように、どんどん記憶から消えている。
ふと、人生は“ところてん”のようだなと思う。
新しい時間を過ごしていると、過去の記憶がその分、ところてんのように押し出されていく。
いくら歳を重ねても、手元に残っている記憶の量はそれほど増えない。
そんなふうにしているうちに、いつか、死ぬ。
存在自体が消えて、もちろん私の記憶もきれいにさっぱり消えるのだから、「忘れないこと」にそんなに固執する必要もないのかもしれない。
そんなことを考えながら神棚を拭いていたら、ああでも、残るものもあるなと、突然思う。
私が持つ記憶は私がいなくなれば無くなるけれど、たとえば息子の身体のどこかに、私の何かは残るのかもしれないな。私の身体の中に、いろんな人の何かが存在し続けているように。
ほんのり哲学的な気持ちになって、そういえば明日は息子が帰ってくる日だ、と思い出す。
2週間ぶりだ。彼はこの期間にスキーが滑れるようになったらしい。私はこの期間に、何ができるようになっただろうか。
早く、会いたい。
画・中田いくみ タイトルデザイン・安達茉莉
◼︎連載・第37回1月23日(日)に公開予定です
佐藤友美(さとゆみ)
ライター・コラムニスト。1976年北海道知床半島生まれ。テレビ制作会社のADを経てファッション誌でヘアスタイル専門ライターとして活動したのち、書籍ライターに転向。現在は、様々な媒体にエッセイやコラムを執筆する。 著書に8万部を突破した『女の運命は髪で変わる』など。理想の男性は冴羽獠。理想の母親はムーミンのママ。小学4年生の息子と暮らすシングルマザー。