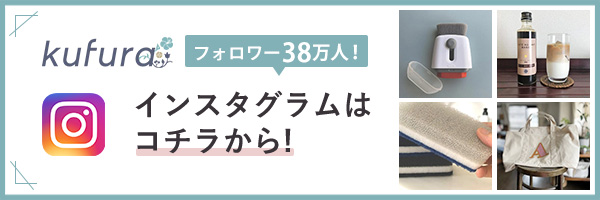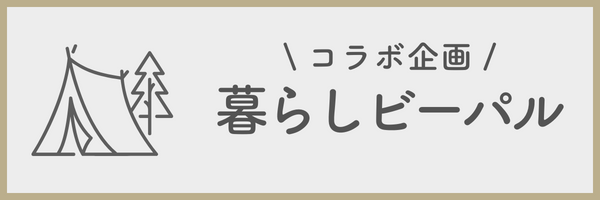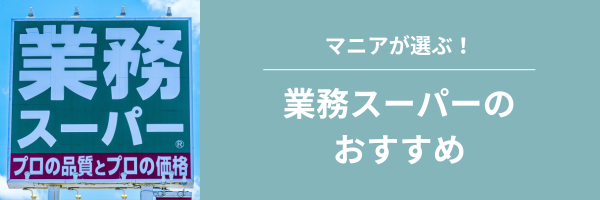“外国語活動”は小学3年生から。5年生からは“教科「外国語」”に
小学校で英語教育が始まったのは2008年度、小学5・6年生を対象に、「聞く・話す」が中心の「外国語活動」として始まった。2011年度にはそれが必修化された。そして2020年度にはさらに大きく変わる。
まず、「外国語活動」の必修化が小学3・4年生に引き下げられる。さらに小学5・6年生の英語には「読む・書く」も加わり、正式な「教科」となる。
「外国語活動」としての目標は、コミュニケーションを図る素地となる資質や能力を高めることだ。つまり、あくまで楽しみながら英語に触れることに主眼が置かれていた。それが「教科」となると、そうした資質や能力を実際につけさせることが目標となる。検定教科書も作られ、成績をつける必要も出てくる。
小学英語の低学年化が進むなか、文科省は2014年度から外部専門機関と連携して「英語教育推進リーダー中央研修」を実施し、英語教育推進リーダーを養成している。取材した日の講師を務める、昭和女子大学附属昭和小学校英語科主任の幡井(はたい)理恵先生も、その一人である。
中高6年間習っても英語が話せない理由
英語には次の4技能がある。
リスニング(聞く)
スピーキング(話す)
リーディング(読む)
ライティング(書く)
まず、幡井先生は講座の中で、日本人が中学高校を通じて6年以上英語を習いながら、英語が話せない理由を、リスニングを例に語る。
「『英語教科で、何を勉強しましたか?』と聞くと、多くの人が『単語を覚えること、それから文法のルールを覚えることを勉強しました』と答えます。『ではリスニングしましたか? どういうリスニングでしたか?』と尋ねると、その多くは教科書の内容をCDで聞くようなリスニングです。通常の会話のやりとりを聞くことのないケースがほとんどです」
ではリーディングについてはどうだろうか。
「『授業では何を読みましたか?』と聞くと、『教科書を読みました』と答える人が多いです。でも教科書を読むときは、自分で辞書などを調べて日本語訳をつけてから読みますよね。内容がすでにわかっているものを音声化しているだけで、本当に“読んでいる”のではないんです」
スピーキングやライティングも同様で、従来の指導法が『使える英語』につながらないのは、知識を頭に入れることばかりに重きを置いて、実際に使う訓練をほとんど行ってこなかったからだと、幡井先生は言う。
すでに習った内容を、英語で学び直す
小学校で英語を教えるようになった背景には、学校教育でこれだけ英語を学びながら、使う機会がないために、知識で終わっていることへの反省があるという。そこで、学んだ知識を「使う」ため、幡井先生が進めているのが「教科連携」といわれる指導法だ。(教科連携の実際の様子は「こんなふうに習いたかった最先端小学英語の模擬授業」の記事へ)
これは、他教科ですでに学習した内容を題材として活用し、「聞く・話す・読む・書く」の4技能を高めることをねらう。全教科を担当する小学校教員だからこそ、教科を超えて英語指導に生かすことができる。
似たような手法に「CLIL(Content and Language Integrated Learning クリル)」というものがあるという。これは、文法構造が英語に似ているヨーロッパの非英語圏を中心に始まった指導方法で、現在は日本でも注目されている。算数や社会などといった教科の内容を英語で学ぶことで、両方の学習を一緒に行うものだ。教科学習と語学学習の割合はほぼ半々で、「英語で教科内容を学ぶ」ことに主眼が置かれる。
これに対し、教科連携では、主眼はあくまで「英語を使う力をつける」こと。そこに教科の既知の学習内容をエッセンスとして加えることで、学習者の関心を引き出そうとする点が異なる。すでに習った内容であれば、英語学習に教科のエッセンスを入れられる。言ってみれば、理科や算数の学習内容を英語でもう一度、触れてみようというものだ。
「教科学習も英語学習も全部つめこんでしまうと、子供たちはいっぱいいっぱいになって、英語嫌いになってしまいます。小学英語で一番大切なのは、英語を好きになることです。そのため教科連携といって、CLILという言葉は使っていません。ただCLILは今、注目を浴びている指導法なので、概念だけでも知っておくと便利です」 (幡井先生)
この教科連携の背後にある考え方について、幡井先生は今年3月に発表された学習指導要領の草案について語った。
知識を持っているだけではダメ
新学習指導要領では、英語だけではなく、どの教科も同じことを目標にして子供を育てていこうとしているという。それは、
(1)何を知っているか、何ができるか
→知識・技能
(2)知っていること・できることをどう使うか
→思考力・判断力・表現力
(3)どのように社会・世界と関わり、よりよい人生を送るか
→主体的に学びに向かう力
である。つまり、知識や技能を持っているだけではだめ、持っていることを使って、生かしていこう、そして人生を歩んでいこう、ということだ。
子供たちが教えたり教えられたりする学習を
英語学習における教科連携が重視されているのも、この考え方からだ。その理論的基盤として、認知・教育学者のハワード・ガードナー教授(ハーバード大学教育学大学院)による多重知能理論があるという。
子供にはさまざまな能力がある。言葉に強い子供もいれば、体で表現するのが得意という子供もいる。まわりの空気を読んで行動する子供もいれば、自分のやりたいことを追求する子供もいる。そこで、ガードナー教授は、子供のもつさまざまな知能を8つに分類した。
(1)言語的知能
(2)論理数学的知能
(3)音楽的知能
(4)身体運動的知能
(5)空間的知能
(6)対人的知能
(7)内省的知能
(8)博物学的知能
今までは英語指導の際に言語的知能だけに意識が向けられてきたが、もっと多くの知能に着目して子供の能力を開花させていこうという考え方だ。 いま注目されている「協働学習」も、子供たちがお互いの能力の違いを認め合いながら、互いに教えたり教えられたりして学んでいくことができる、一歩先を行くグループ学習だ。
幡井先生はこれを英語の授業にも生かしていきたいと語る。その模擬授業は、「私もこういうふうに英語を学びたかった」と思えるものだった。
文・写真/小島和子(講義風景)
(初出 まななび 2017/09/04)