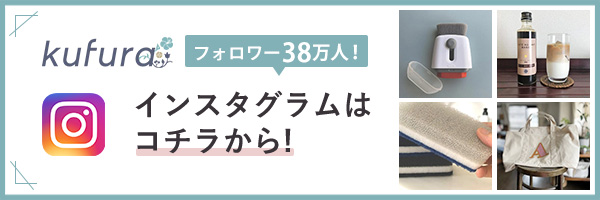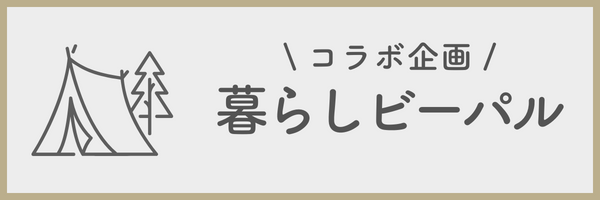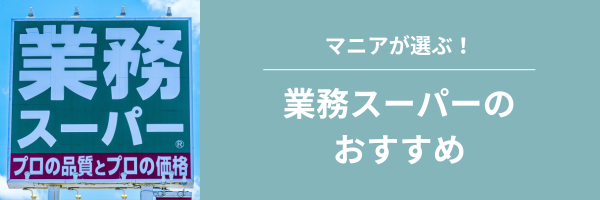「君の名前で僕を呼んで」に潜む、美しくも危険なメタファー2つ
null1:「Later」(後で)=成熟

北イタリアのヴィラで過ごす夏の休暇。でもこの夏はいつもと違った……。©Frenesy, La Cinefacture
17歳のエリオ(ティモシー・シャラメ)は、夏の休暇を毎年両親と一緒にアメリカから北イタリアへ飛び、17世紀に建てられた美しいヴィラで過ごしていました。美術史教授の父(マイケル・スタールバーグ)と翻訳家の母(アミラ・カサール)とともに、ピアノやギターを奏でたり、読書や作曲に勤しんだり、ときには現地のティーンエイジャーと夜遊びをしたり。
現地のゲストを招いてパーティーを開き、フランス語、イタリア語、英語を駆使して、美術や古典文学について語る……絵に描いたような知的な家族です。
1983年、エリオのヴィラに訪れたのは、父のインターンで大学院生のオリヴァー(アーミー・ハマー)。オリヴァーと出会った瞬間、学生とは思えぬ自信に満ち溢れた彼に、エリオは少し反発を覚えます。なぜなら、究極の知性を体現する父と対等に議論を交わせるだけではなく、オリヴァーは健康的で完璧な美しさも兼ね備えていたから。

オリヴァーが言う「Later」に不思議な反発を覚えるエリオ。©Frenesy, La Cinefacture
そんなオリヴァーの口癖は「Later」。「Later」はアメリカの一般的な挨拶で、「後で」、「またね」、「さよなら」の意味として使われます。挨拶以外には、例えば、子供に宿題をしなさいと言ったら、「後で」という返事としてもよく使われる言葉。
誰もが使う「Later」ですが、オリヴァーのややぶっきら棒な口調には、有無を言わせぬ強引さを感じ、イラ立ちを覚えるエリオ。

オリヴァーに惹かれていくエリオ。そしてオリヴァーもまた……。©Frenesy, La Cinefacture
この「Later」は、“成熟”のメタファーのように思います。17歳のエリオは、現地のフランス人の女の子マルシア(エステール・ガレル)とセックスを試すものの、まだ本当の恋を知りません。性への興味はありますが、そのか細い身体はまだまだ子どものよう。大人顔負けの早熟な才能と知性をもったエリオは、頭脳の成熟度に心と身体がついていっていないことを自覚しています。だからこそ、成熟した男らしいオリヴァーの何気ない「Later」に羨望し、嫉妬するのです。あたかも、“子どもの自分”に「Later」と、さよならをしたいかのように……。

2:「ダビデの星」ペンダント=アイデンティティー

ダビデの星のペンダントを欠かさないオリヴァー。©Frenesy, La Cinefacture
作中、オリヴァーが堂々と、“ダビデの星”のペンダントをつけていることにエリオは驚きながら、彼にこう言います。「僕も昔はこういうペンダントをしていた」。ダビデの星は、ユダヤ教やユダヤ民族のシンボル。実は、エリオの一家もユダヤ系アメリカ人でした。

エリオの“目覚め”を優しく見守る美しい母アネラ。©Frenesy, La Cinefacture
しかし、“私たちは自由なユダヤ人だから、わざわざユダヤ人らしくしなくてもよい”と言う母の影響で、ダビデの星のペンダントをつけなくなったのだとエリオはオリヴァーに話します。このシーンは、迫害されてきた歴史を背負うユダヤ人の価値観が表われていて興味深い所。自分のルーツをオープンにするかどうかは別として、自分のアイデンティティーを決めるのはほかの誰でもなく、自分自身でしかない――ということを、エリオの母は彼に教えたかったのではないでしょうか?
そして、このダビデの星のペンダントは、ユダヤ人としてのアイデンティティーだけではなく、エリオにとっては“セクシュアリティ”のアイデンティティーを指しているようにも受け取れます。

夏が終わったらオリヴァーは去っていく……。初めて恋の痛みを知るエリオ。©Frenesy, La Cinefacture
なぜなら、オリヴァーと心を通わせてから、エリオは再び、ペンダントをつけるようになったから。ホモセクシュアリティがまだまだタブーだった1980年代に、男性をも愛せるというセクシュアル・アイデンティティーを、やっとエリオは自認できたのです。

自分の世界観をエリオに語る父パールマン教授。©Frenesy, La Cinefacture
男性同士の恋を描いた映画はたくさんありますが、本作が一線を画している点は、子どものセクシュアリティの目覚めを両親の視点からも描いているところ。映画の最後に、父がエリオに語りかける言葉は、涙なくしては観れません。筆者はこのシーンから映画が終わった後も、しばらく涙が止まりませんでした……。子どもの見守り方について考えさせられますよ。
彫刻のような美しさのなかに野生的な官能を秘めたオリヴァー役のアーミー・ハマーと、ヨーロッパの洗練された雰囲気を醸すエリオ役のティモシー・シャラメが、みずみずしく艶っぽい演技(とセックスシーン!)で私たちを魅了する永遠のラブストーリー。久しく忘れてしまった、胸のトキメキやざわめき、恋の痛みや切なさが一気に甦る傑作です。
【作品情報】
4/27(金) TOHOシネマズ シャンテ 他 全国ロードショー
配給:ファントム・フィルム
提供:カルチュア・パブリッシャーズ/ファントム・フィルム
©Frenesy, La Cinefacture