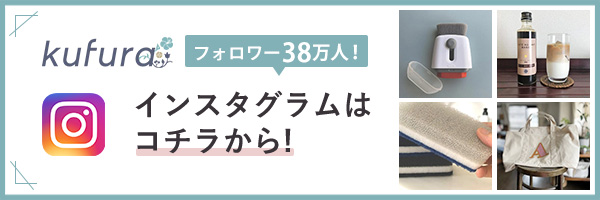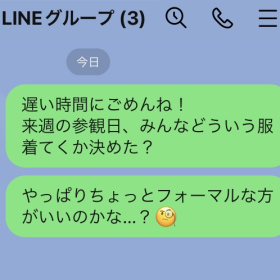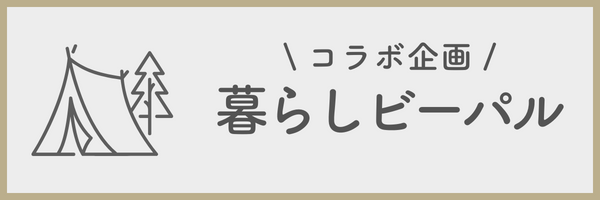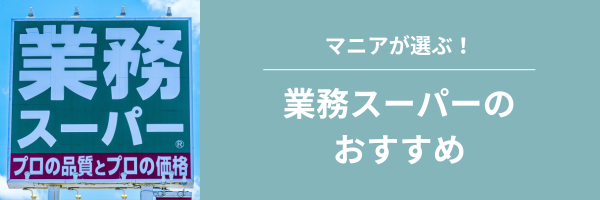この子の命を守らなきゃ!強い思いと自責の念
null
子どもを持ってみて分かるのは、子育ては思い通りにならないということ。しっかり育てなければいけない、と思って子育てに臨んでいるのに落ち込んでしまうことは多々あります。
その最たる出来事は、子どもの怪我や病気ではないでしょうか。特に入院するようなケースの場合、親も子も面食らってしまいます。
さいかち学級にやってくるママたちは、どんな反応なのでしょうか。
「親は、この子をちゃんと育てなければいけない、社会に適応できるようにしなければいけないと思っています。そのためには、まずこの子の命を守らなきゃと。
そして、子どもが良くなるようにと、いっぱい叱ってしまい、理不尽なことを押し付けたりもしてしまう……。
そんな日常の中で子どもが病気になると親もまた傷つくのです。ちゃんと子どもを育てられなかった自分、とレッテルを貼って、ダメな自分だと思い込んでしまいます。
と同時に後悔の思いが押し寄せてきます。
そういえばあのとき頭が痛いって言ってたのに、なぜ気づいてあげられなかったんだろうか、って。大丈夫だというから学校に行かせちゃった、と。
特に、小児がんにかかってしまった親御さんは、僕が“それは関係ないと思いますよ”と言っても聞き入れず、すべてが親の自分の責任だと思ってしまいます」
親も「助けて」と言える人を作っておく
子どもの病気がきっかけになって、家族というチームの和ができる人たちもいれば、現実を突きつけられて「私はもう知りません、何もできません」と受け入れられずに拒否してしまう人も少なくないそうです。
その結果、家族が壊れたり、周囲の大人たちの関係性がうまくいかなくなった人も。
「どうやって親御さん、きょうだい、家族を支えるかは、常に医療者と話し合いながら考えています。壁にぶつかったとき親もまた”助けて”といえばいいのです。
それは自分の夫かもしれない、親かもしれない、友達かもしれない。助けてと言える人を作っておくことです。
子どもには助けてと言っていいんだよ、といっているくせに、自分では助けてと言えないのは問題です。教師もそうですけれど、弱みをみせちゃいけないなんてことは絶対にないんです。
“お母さん辛くて、おばあちゃんに話を聞いてもらった”でいいんです」
子どもにいろんなモデルを見せることは、子どもの生きる力につながると副島先生は言います。副島先生は、病棟にいるママたちにも積極的に声をかけます。
「自分の時間を持ってくださいね」と。
教師は仲人であり、通訳だ
null保育園や幼稚園に入れば、今度は小学校。小学校に入れば、中学はどこに進んだらいいのだろうか、と病気を抱えて生活している子の親たちの悩みは尽きません。その段階段階で、新たな不安や心配が襲ってきます。
「どの親御さんもそうですが、子どものライフサイクルに合わせて悩みも変わります。病気を抱えたお子さんの親御さんの場合は、最初は病気と闘えばいい。しかし上に進めば進むほど、選択肢が少ないことを知って愕然となるのです。
子どもは夢を持っています。中学校に行ったら、あれもやりたい、これもやりたい。でも機械をつけているから、あそこの学校は受け入れてくれない。学校に行けると言ったのに1校しかなかったというケースばかりです。
学校は命が大事だから受け入れるのを断念するのは分かりますが、受け入れの準備をして、子どもたちにも親御さんにも選択できるような学校制度にしてほしいですね」
副島先生が猛烈に後悔していることが一つあると、言います。
それは次の詩を書いた、子どもとの別れでした。
ぼくは幸せ
お家にいられれば幸せ
ごはんが食べられれば幸せ
空がきれいだと幸せ
みんなが
幸せと思わないことも
幸せに思えるから
ぼくのまわりには
幸せがいっぱいあるんだよ
「子どもたちのことで、明日でいいと先延ばしするのはやめようと決めました」
nullこの少年は先天的な病気で、小さいころから入退院を繰り返していたそうです。6年生になり、1年ぶりに退院する日これを書きました。
この1カ月後、再び入院。副島先生は午後7時過ぎに連絡を受けましたが、仕事が終わらず、面会時間には間に合いませんでした。院内学級を離れ、病棟が見える場所に来たとき、
「明日会いに行くからね」
そう病室に向かって語りかけたそうです。しかし、彼はその日の未明に亡くなりました。
「どうして行かなかったのか。その日以来、子どもたちのことで、明日でいいと先延ばしするのはやめようと決めました」
自分がやれることはすべてやろうと、副島先生は大学院で子どもの心理を指導、院内学級のアドバイザーに加え、東日本大震災後のボランティア、子どもホスピスの設立、講演活動など多くの活動を精力的にこなしています。
「今の教育は、学校制度に適応できる子どものための教育です。病気の子もいれば障害のある子もいる。法律や制度、予算をつけて教員を配置するなど、みんなが安心して通える学校にしてもらいたいです。そのためには僕も努力を惜しみません」
そう話すと赤鼻をつけて、とびっきりの笑顔を見せていました。
副島賢和(そえじままさかず)
1966年、福岡県生まれ。都留文科大学卒業後、東京都の公立小学校の教師に。2001年、東京学芸大学大学院修了。2006年より、『さいかち学級』の担任。14年から現職として『さいかち学級』のアドバイザーを務めている。著書に『あかはなそえじ先生のひとりじゃないよ ぼくが院内学級の教師として学んだこと』『心が元気になる学校』。