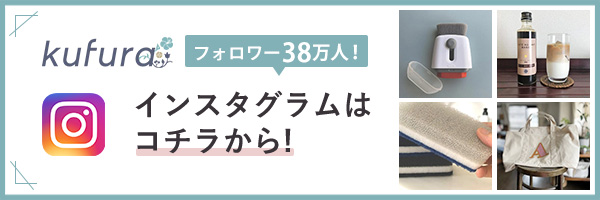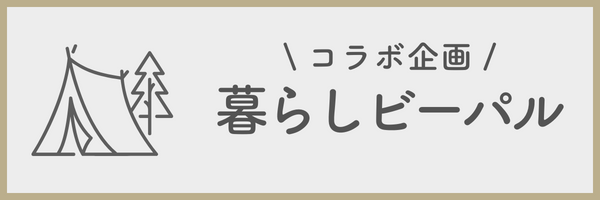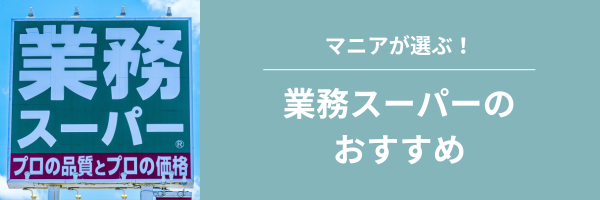「ばあばはもう少しで死んじゃうの?」
null2年ほど前のことだったろうか。
北海道にいる母から連絡があり、両親のテニス仲間だったおじさんが亡くなったという。私も小さい時から可愛がってもらったおじさんだった。
お夕飯の席でその話を夫にしていると、当時7歳だった息子氏が、ばあばのお友達、死んじゃったの? と聞く。
どうして? と尋ねるので、病気だったんだって、と答えた。
そんな会話があった、その日の夜。
布団の中で息子が私のところにすり寄ってきた。
「ねえ、ばあばのお友達が死んじゃったってことは、ばあばももう少しで死んじゃうの?」と聞く。
ばあばは元気だから大丈夫だと思うよというと、
だけど、ばあばはもうすぐ70歳になるでしょ。じいじは、ばあばより歳上だよね。寿命まではあと何年あるの?
もし、じいじと、ばあばが寿命まで生きたとしたら、そのとき僕は何歳? と尋ねてくる。
寿命は誰にもわからないけれど、いまは元気だよ、と答える。
心配なの? と聞くと、頷いた彼の目にみるみる大きな涙がたまる。
「だってママは、僕を産むのが遅かったでしょ。だから、クラスのみんなのママより、歳とってるんだって。ママが歳をとってるってことは、じいじもばあばも、お友達のじいじやばあばよりも歳をとってるんでしょ」
そういえば以前、彼に、高齢出産について説明したことを思い出した。
「ママがもっと早くに僕を生んでくれてたらよかったのに。そしたら、じいじもばあばも、こんなに歳をとってなかったのに」
と、彼は泣く。
夜になると、生死の境目が揺らぐのはみんなそうなのだろうか。
息子氏は、言葉を覚えてすぐの頃から、ことあるごとに死んだらどうなるのかと、私に尋ねる。
何度も何度も死ぬことについて尋ね、そしてそのたびに小さくすすり泣く。
「ぼくね、死んでも覚えていたいの」
死んだ後の記憶についても、よく話をした。
「もしも僕が死んじゃったとしたら、覚えてられる?」
「そりゃ、ママはキミのこと忘れたりしないけど」
「違う。僕が死んだら、僕はママのことを覚えてられる?」
「あ、そういう意味か。それはわからないなあ」
「どうしてわからないの?」
「だって、死んだことがある人と、誰も話したことないから」
「じゃあ、ママはどう思う? 死んだ後も、覚えてられると思う? ママの考えでいいから」
ちょっと考える。ちゃんと私の考えを話した方がいいなと思って、彼の方に体を向き直した。
「うーん、わからないなあ。ママは、死んだらなにも覚えていないんじゃないかという気がするけれど」
「ぼくはね、死んでも、ちょっとだけは覚えていられると思うんだよね」
「うん」
「そしたらぼくは、ママとパパとじいじとばあばのことを思い出すと思うの」
「うん」
「どうしても覚えていたいの」
「そうなのね。一番覚えていたいのはどんなこと?」
「この間、ママがぼくに言ってくれたでしょ」
「?」
「ママが今までで一番嬉しかったのは、ぼくが生まれてきてくれたことだよって」
「……」
「あれね、ぼくね、死んでも覚えていたいの」
「……」
「忘れたくないのぉぉぉ」
「……そっか」
そうか、たしかにずいぶん前に、言ったことがあるな。
覚えてくれているんだね。
彼をそっと抱きしめる。
夜は、生死の境目がゆらっと揺れる。
私のパジャマに顔を埋めている息子氏からは、鼻をすする音だけが聞こえる。
だけど、と、私はふと思う。
おい、ちょっと待て。
とんとん。
「ん?」
「あのさ」
「……うん」
「ママ、ひとつ提案したいことがあるんだけど」
「うん……提案ってなに?」
「ママが、こうしたほうがいいんじゃないかと思うことを、発表したいと思います」
「はいどうぞ」
「死んだあとにも、覚えていたいといってくれてありがたいんだけれど」
「うん」
「いったん、ママもキミも、いま、生きてるじゃん?」
「うん?」
「ばあばも、いま、生きてるじゃん?」
「うん」
「死んだ後にどうなるかはわからないけどさ、生きてるうちのことは自分のきもちしだいで、そこそこコントロールできると思うわけ」
「うん」
「だから、いったん、生きてる間にできるだけ仲良くしない?」
「……」
「キミ、さっきさ、ママなんか大嫌い、こんな家、出ていくって言ったよね」
「……」
「ママが『ゲームより先に明日の学校の準備してね』って言った時」
「……」
「あとさ、この間、ばあばが来てくれた時にもケンカして、ばあばなんか北海道に帰っちゃえ。もうこなくていいっていったよね」
「……」
「いや、死んだあとに思い出してくれるのも嬉しいんだけど、いったん、生きてるうちにできるだけ、優しくしあって、仲良くしたいと思うんだけど」
「……」
「……どう?」
「……」
「……できそう?」
「……うん、わかった……」
「じゃあ、指切り」
「……うん」
いっぱい泣いて疲れたのか、彼はそのまますぐに寝落ちした。
それでもきっとこの指切りのことを、私たちは、明日には忘れる。そしてまたきっとケンカするんだ。宿題が先だの、お手伝いが先だの、風呂入れだの、ゲーム片付けろだの。
でも。
彼が、死んでも僕は覚えていたいといった、その言葉をきっと。
いつか必ず、これから何度も、私は思い返すんだと思う。
思い出したり、忘れたり、また思い出させたり、ケンカしたりして、そして、いつかは、本当に死ぬ。本当に別れることになる。
その時に、何かひとつ記憶を持っていけるとしたら。この日のことがいいなって、暫定的に、思った。
そして。
「でもまあやっぱり今はまだ死んでいないから、生きてるうちに、できるだけ大切にしよう」
と、彼に言った言葉を今度は自分に言い聞かせる。
子どもにかけた言葉のほとんどは、ブーメランなのだ。
・・・・・・・・
この出来事があってからしばらくのち。
私は、このときの会話を鮮明に思い出すことになる。
じいじが、つまり私の父が、余命数カ月と宣告された。
(つづく)
タイトル画・中田いくみ タイトルデザイン・安達茉莉
◼︎連載・第9回は12月27日(日)に公開予定です
佐藤友美(さとゆみ)
ライター・コラムニスト。1976年北海道知床半島生まれ。テレビ制作会社のADを経てファッション誌でヘアスタイル専門ライターとして活動したのち、書籍ライターに転向。現在は、様々な媒体にエッセイやコラムを執筆する。 著書に8万部を突破した『女の運命は髪で変わる』など。理想の男性は冴羽獠。理想の母親はムーミンのママ。小学3年生の息子と暮らすシングルマザー。